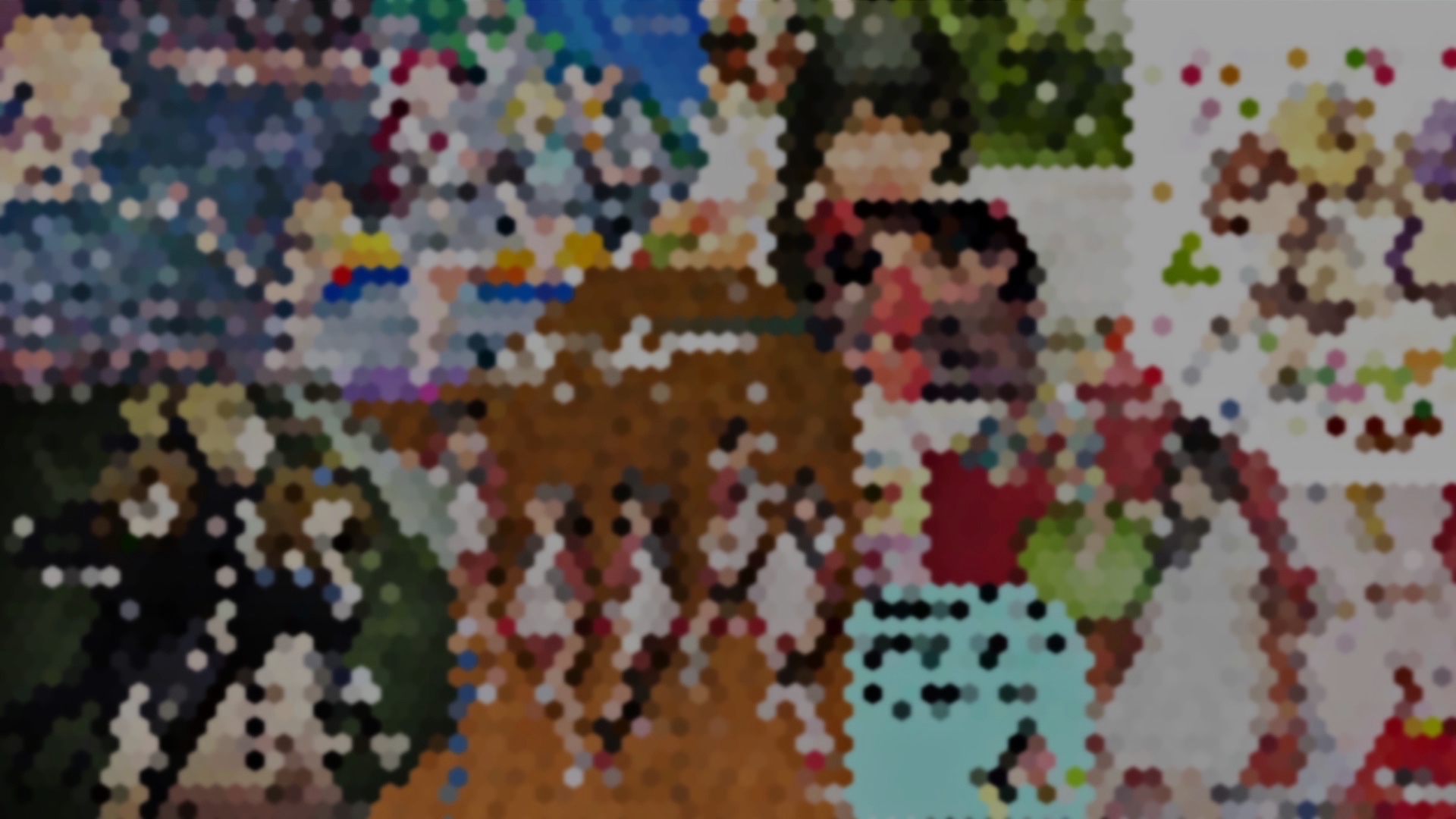目次
6. Blkの考察と応用
ここまででBlkを6種類に分けましたが……
読んでいて疑問に思った方もいるかもしれません。「長3も短3もどっちもあり得るとか、スラッシュコードともテンションコードとも見れるような例もあるんじゃないか?そういう時、どっちに分類するんだ?」と。
実のところ、Blkは同時に複数の系統に属しえます。それも、当然のようにです。上図ではツリーの形で表現したものの、実際の音楽で起きることはもっと経時的で玄妙なものなのです。
単にBlkのコードトーンが鳴っているだけでは何も確定せず、混沌としたままです。それが前後の文脈や同時に鳴るメロディなどによって、一致しないものが切られていって可能性が絞り込まれていくというプロセスを踏みます。
だから「複数の系統に当てはまることがある」というよりかは、「ひとつに定まるまでは常に複数の可能性が重なった状態にある」というのがよりイメージとして正確です。
これは何も珍しい話ではなく、例えばパワーコードが単体でポンとなっただけでは、そこに乗るスケールがメジャー系かマイナー系かなど知るよしもない。そこまで築いてきたトーナリティ、ルートの音度、フレーズとの絡みなどがあって初めてそれが見えてくるというのと、本質的には同じ話です。
多義性論の世界
VIII章のこれ以降の記事では、この「和音の意味の多重性・不確定性」がひとつのテーマとなって進んでいきます。我々はどんなふうにして和音の意味を特定するのか? 何を予期しながら音楽を聴くのか? この記事でも少し、そういう音楽の深遠なところに触れてみたいと思います。
文脈の多重性
Blkの中でもとりわけ♯IVblkは使い勝手がよく、用例も多く見られますが、その理由は♯IVblkが同時に抱え込める文脈の多さにあるという仮説が立てられます。
まず「augの反転」と見たとき、アッパーのI+はオーグメントの使いどきとして非常に有名なパターンです。手前に来るのはI、後続はIVが典型。
あるいは「偶成和音」とみても、♯IVというルートはVとIVの間のクロマティックな経過地点となれる。ルートの音度がダイアトニックだとそうはなれないですね。
そして♯IVøといえばポップスの必殺技としておなじみだし、♯IV7はポップスでこそ頻用されないですが、代理ドミナントの一種としてジャズのボキャブラリーにはあります。そしてこの二者はどちらにしても、後続としてIVを指向します。
特殊例であるホールトーン系を抜きにしても、これだけの可能性を♯IVblkは内包しています。この点に関して♯IVは全ルートの中で一番です。
- IVΔ7III7VIm9VIm/V
IVblk
「文脈が多重化していれば、それだけコード進行に組み込みやすい」という仮説は、前回のナポ六の解釈でもカレーうどんに喩えて説明しましたね。
♯IVはBlkに至る道筋がたくさんあるから必然的に遭遇率も高くなるし、またリスナーもこれを受け入れやすいのだと思います。何なら「各リスナーが、7・ø・augのうち最も聴きなじみのあるクオリティで認知して、その亜種として受容している」という可能性すら考えられます。
だからBlkを論じるうえでは、3rdが不在であるという特徴は凄まじく重要で、これが長3でも短3でも実際に鳴ってしまったら、それは単なるドミナントセブンスだったり、ハーフディミニッシュのインスタンスと化し、こうした奥深い広がりは全て失われてしまいます。
他のルートだと…?
文脈の多寡は、ルートによって異なります。例えばルートがIのBlkは、解釈の可能性がさほど広がりません。
「augの反転」と見るならアッパーはII+,♯IV+,♭VII+のいずれかですが、どれだとしても決して聴き馴染みのないものです。またトニックたるI度がルートでは、クロマティックな経過和音にもなり得ません。
そして、トニックコード上でハーフディミニッシュを形成するなんてことも、まあ滅多にないですよね。けっきょく現実的な筋としては、二次ドミナントのI7を過激化させたのだという、属九系だけしか残らないのです。
- IVΔ7III7VIm9Vm7I7(-5,9,omit3)
こういった感じの使い方になります。♯IVblkの時と比べると、「ドミナント系」の蓋然性が突出して高い一党独裁のような状態です。
I7とIV7だったら、頻繁に使われるのは前者。でもIblkと
IVblkだったら使いやすいのは後者。なぜ? となった時に、この文脈多重性が有力な答えとして浮上してきます。
文脈の支えがないので、人によってはこの使い方だと“aug感”があまり感じられないという可能性もあるかと思います。言い換えればそれは、I上だとRt7thの結束力が強くて、ベースとアッパーが認知のうえで切り離されないという可能性です。
リスナーの認知を操る
同じ構造のコードでも、人によって意味の受け取り方が変わる。この特徴は、何か実践的なアイデアに昇華できそうです。そこで次は、前後関係やメロディの乗せ方を細かく調整することで、聴き手の認知をある方向にリードするような応用を考えます。さながらメンタリストのように、わずかな音のしぐさによって人間の意識をある方向へと誘導する、マインドコントロールをするのです!😈
こちらはCとC+の繰り返しから始まり、8小節目でFblkが登場、そこからBΔ7へ進み、それをIVと見立てて4-5-1-6の進行でF♯メジャーキーへ転調するという例です。トライトーン転調にもかかわらず、実にスムーズですね。
一見すると単なるピボットコードですが、実は知的なトリックを実行しています。Blkに入った瞬間はオーグメントっぽくふるまい、しかし出ていくときにはドミナントセブンスっぽい顔をしているのです。
「CとC+を繰り返している」という前方の文脈があるので、Blkが鳴った瞬間は「ああ、またaugの繰り返しか」から始まります。そして今回はフレーズのインターバルを慎重にコントロールし、Augの香りをちょっとずつ弱め、ゆっくりと「スラッシュコード系」から「ドミナント系」へと変質し、終盤でM3rdであるA#音を鳴らすことでドミナントセブンスとしてのクオリティを確定させています。ほんの1小節の間に、目まぐるしいイベントが起きているのです。
カメレオン戦略
転調の際に転入先のスケールを先んじて演奏するというテクニックはよくあります。しかしコードクオリティ自体が変質していくというカメレオンのような挙動は、Blkのように「文脈多重性」の強いコードにしかできません。
我々はベース音を聞き取る能力には長けていませんし、そこまでの流れによる誘導もあって、コードチェンジの瞬間はウワモノのC+がまず耳に飛び込んでくる。しだいにベースとウワモノが繋がって、ひとつのドミナントセブンスコードとして見えてくる。人間の脳の処理速度の遅さを利用したトリックというわけです。
「Blackadder Chordは、それ自体は実体をもたない抽象概念である」という言葉の意味が、だんだん実感を伴って理解できてきたのではと思います。
Blkから得る教訓
「カメレオン戦略」は、ひとつのコードの内部でコードの見え方を変化させていくという面白いテクニックでした。これは図らずも、現行の一般的なコード理論が利便性のために捨ててきたものにスポットライトを当てる行為でもあります。具体的には、以下のような点です。
| 通常の発想 | 「カメレオン戦略」の発想 |
|---|---|
| コード単位で音楽を見る | コード内部の駆け引きまで見る |
| 後方までふまえて総括的な分析 | 一瞬一瞬の体験を分析 |
| クオリティは一つに定まる | クオリティには認知の揺れがある |
| 不確定要素は解釈で補完する | 不確定要素はその不定性を利用する |
「通常の発想」の方にリストアップされているのは、いずれもコード理論の基盤となるベーシックな考え方ですよね。でも「カメレオン戦略」の考え方は、全てその基盤から外れた発想で出来ています。だから先ほどの例を「通常の発想」で分析したら、次のような解釈に落ち着いてしまう可能性は十分にあります。
こういった説明は一見エレガントですが、シンプルな論には文字どおりシンプリフィケーション(単純化)が伴います。「アッパーがたまたまaugである」という情報を捨てればデータサイズは節約できますが、その代わり「カメレオン戦略」のようなアイデアは出てこなくなるし、何よりリスナーが“aug感”を感じるというのは事実なのに、それを理屈で覆い隠すのは本末転倒でしょう。
理論は確かに音楽をシンプルにしますが、それは音楽をシンプルに見せているだけで、音楽そのものがシンプルになることはないというのは、忘れないでいてください。
解像度と死角
VII章の和声学やメロディ編V章のハーモナイズ論を通じて既に理解していると思いますが、ノーマルなコード理論の解像度というのはそんなに高くありません。「カメレオン戦略」は、その死角をつく技法だと言えます。
これは序論でも述べたことですが、なまじ理論に詳しくなると、理論で見える部分だけしか見なくなってしまう、それで音楽の全てを見た気になってしまうという危険は、VIII章まで来た今だからこそ改めて警鐘を鳴らしたいところです。
こうしたコード理論の“死角”については、この先の「ポリセミー論」で詳しく論じることになります。今回はその準備運動という感じでした。
7. 総括
さて、長かった説明もこれで終わりです。最後に内容を総括していきます。
呼称と語法について
Blackadder Chordにはいくつか他の呼称もありますが、このサイトでは、ひとりで7曲も実例を見つけて採譜もして動画にしてくれたJoshua Taipale氏に敬意を示して、この名を一貫して用います。
 Joshua Taipale氏
Joshua Taipale氏また「Blackadder Chord」という語の使い方については、次のような意識で用いるのがよいかと思います。
- 系統やスペリングを問わない「総称」として用いる。
- 文脈が1つに絞りきれず、コードネームが明白でないときに用いる。
「スペリングが定まっていない状態の和音をどう表記するか」は、現行のコード理論ではなあなあになっている領域です。Blkのように分岐の激しいコードに対して総称が用意されていれば、都合のよいことでしょう。
例えば属七系だとハッキリ分かる時には単にコードネームで書くか、さもなくば「長3系のBlk」「属七系のBlk」「Blkの一種」といった風に表現するのが最適だと思います。
分析の際にはぜひ「アッBlkだ」で終わらせずに、どの系統は可能性が切られていて、どの系統が濃く残っているかといった繊細なところを分析すると、得るものが大きいはずです。
文脈のターミナル
さて、最終的に「Blackadder Chordとは何か」と訊かれたら、それは[0,2,6,10]のフォーメーションを持つコードであると、それ以外にありません。
しかし、どんな理論システムでこれを観察するかによって見えてくるものが違います。これは「ナポリの和音」と似ていますね。たくさんの文脈が交差する“ターミナル”であり、通る“路線”を把握していればそれだけ自由に“乗換え”ができるという、すごく知性を刺激するコードでした。
トップへ戻る