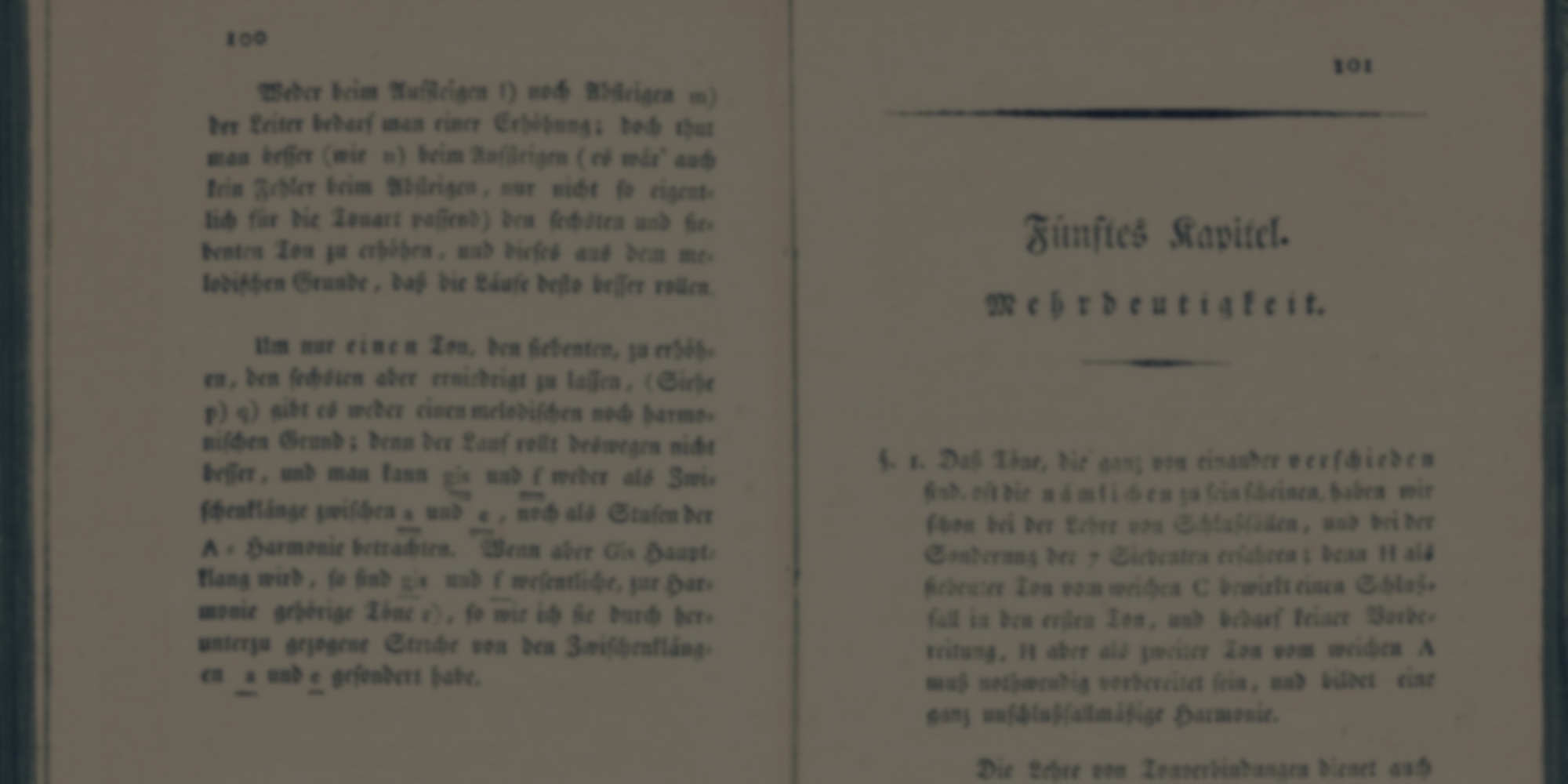目次
用語の紹介に関して
ここから本論に入っていくわけですが、またメロディ理論やメタ音楽理論同様、新しい用語の設定が多くなるため、「〜と呼びます」とあればそれはみな独自に提唱する語彙、「〜と呼ばれます」とあればそれは先行する理論書や論文で既に使われている語彙、という風に区別します。
3. 構造と文脈
ポリセミーをコントロールするためには、まず多義状態にある和音がいかにしてモノセミックへと収束していくかのプロセスをしっかり掌握する必要があります。和音の意味を識別する手がかりとなる要素はいくつも考えられますが、代表的なものは以下のとおりです。
- ①構造情報
その和音と共に使用している音とその偏り、配置、低音部が何であるかなど。 - ②前方文脈
前方に形成されるトーナリティや、直前のコードとの声部連結 - ③後方文脈
後方に形成されるトーナリティや、直後のコードとの声部連結 - ④時間文脈
和音がリズム上のどの位置にどんな長さで置かれているか - ⑤文化文脈
ジャンルや時代、楽器の特性、編成の特性などから生じる情報
簡単に言えば①はコードが鳴ってる瞬間そのときの文脈非依存の情報です。ただどの音が鳴っているかだけではなく、長さや高さや配置など、全ての情報がコードを識別するヒントになります1。
②と③が前と後ろ、④は前後ひっくるめた時間上の配置、⑤は音響そのものを超えたコンテクストです。④,⑤はここで論じてもあまり実りの少ない部分なので、①〜③が論の中心になります。通常のポピュラー音楽では、始まって2〜3小節もあれば、使った音やメロディラインからトーナリティが形成され、以降はその文脈に基づいて十分に識別がなされます。そうなった後は、たとえ①構造情報に欠落があっても、そこまでに築かれたトーナリティを元に、おおよそ識別は可能です。
逆に言うと、いざノンダイアトニックコードが差し込まれると、そこまでに築きあげたトーナリティが揺らぎはじめ、ポリセミーの門が開くわけですね。ノンダイアトニックの音が入ったとき、そこからどんな環境を第一に想像するかは、個人差もあるでしょう(IVmが来たときIVmΔ7を想起するかIVm7を想起するかなど)。
4. ピボットコードの多義性
まずポリセミーへの理解を深めていくにあたって最適であろう題材が、「ピボットコード」です。誰にとってもわかりやすい、日常的な「意味の重なり合い」が発生している場面ですからね。
こちらはピカルディ終止のVIが、転入先のIを兼ねているというピボットの典型例。ピボットコードは、前方文脈と後方文脈とで異なる2つの解釈が同存しているというアンチノミー(二律背反)によって成立しています2。
ただその重なり方には個性があるはず。手前の文脈を強く残すタイプ、後方の文脈に寄り添うタイプ、ちょっとずつ遷移していくタイプ…。そこを具体的に観察することで、意味がいかに曖昧になり、その多義性がどんな風に収束していくかを理解します。
共通音と特定音
VI章を抜けてきた私たちは、キーの確定にはスケールが大いに影響していることを知っています。奇数度だけでなく、スキマとなる2・4・6度がどう埋まるかで、示唆されるキーが変わってくる。上の「僕のギター」の例では、コードはトライアド、メロはRtとなっていて、1・3・5度以外の情報が全く明かされていません。
「G♭メジャーキーのピカルディ終止」と、「E♭メジャーキーの主和音」では、ほんとうは6・7度の音が異なっているんですよね。今回の例は、それを言わないことで中立を保ったパターンであると言えます。
このとき共通している1〜5度の音は、ときに「ピボット・ノート」と呼ばれたり、もしくは単に共通音Common Toneなどと呼ばれます。ピボットコードというのは要するに、転調前後のスケールに共通するピボットノートから選抜して作ったコードということになります。
一方、ポリセミー論においては、ふだん注目されない「非共通」の音の方も重要になりますので、これをそれぞれの音階の特定音Eigentoneと呼びます。ノンダイアトニック音の登場により生じたポリセミーは特定音を用いることで絞り込まれていき、やがては和音の意味を識別可能な状態になります。
- 特定音 (Eigentone)
- 和音の意味が複数考えられる際に、その意味を示唆する音階たちのうちいずれかだけが有していて、それゆえ意味の特定に利用できる音のこと。
- 例えば文脈の候補が3つあるとき、それを2つにまで絞り込んでくれるような音も、広義の「特定音」に含めるものとする。
- 「共通だけど異名同音の綴りが異なる音」に関しては、それがいくら鳴っていても文脈の特定には繋がらないので、「特定音」には含めず「共通音の中の特別な存在」として扱う。
特定音を鳴らすというチョイスは積極的に意味を確定させにいく行為であり、逆に特定音を鳴らさなければそれだけ意味が不確定な時間が続くということになります。
リアルタイムの音認識変化
こんな初歩的なピカルディ終止の転調でも、認知の側面では面白い出来事が起こっています。
- E
B
CmA
こちらはサビ冒頭の4小節で、明確にE♭メジャーキーの1-5-6-4が描かれていますが、最初の2コードだけ見ればB♭メジャーキーの4-1ととれないこともない。メインメロやウワモノを含めても、この2キーの判断ポイントであるA/A♭の音が鳴っていないので、可能性としては生きているはずなのです。
- E
B
D7(-9)Gm
こんな風に、3-4小節目次第ではB♭キーへ行く未来も考えられる。しかし実際に楽曲を聴いたときにこのような展開を想像するリスナーは、まあいないでしょう。それぞれのキーの特定音であるA/A♭が登場する前からもう、私たちはE♭キーだと判定を下しているのです。何故なのか?
文脈の慣性
別に難しい話ではありませんね。E♭のコードは転調前のキーでVI、トニック機能のコードです。だから特段の示唆がない限り、このE♭は第一にトニック系のコードとして認知される。EB
と来ればそれは第一にT–Dに聴こえる。そういう感じですよね。
それからもうひとつ、転調前のG♭メジャーキーでは、A音にはフラットがつきます。だからそれが解除されたという特段の示唆がない限り、A♭音を含むトーナリティ環境を想起しやすいということも考えられます。
つまり、変化が示唆されない限りは、そこまでにあった文脈を継承するような傾向が私たちにはあるわけですね。比喩的な言い方をすれば、ここにもまた音楽の「慣性」が存在しているということです。この“慣性”の存在は、この先ハイレベルなポリセミーを扱うときに重要になってきます3。
リアルタイム性を意識する
ここから分かることがもうひとつ。当たり前のことなのですが、ノンダイアトニックコードが鳴った瞬間にどう感じられるのかは、「後方文脈」ではなく「前方文脈」次第です4。
私たちが「分析」をする時には、うしろ4小節くらいをじっくりと眺めて、それで「ハイ、E♭メジャーキーですね」と結論づけるわけですが、そうじゃなくて、リスナーがリアルタイムで知覚する音認識を考えることがポリセミーでは重要です。
想定・判定・確定
この音認識変化を正確に論じるために、語彙を明確にして共有したいと思います。まずある和音が入った瞬間に何らかの意味を想起する段階を「想定」、そこからある程度の情報が与えられて、特定の意味をハッキリ認知する段階を「判定」、音構造が実際の音として明示され、他の可能性が(ほぼ)確実に排除されたと言える段階を「確定」と呼び分けることにします。
「想定」については第1想定、第2想定…が同時に発生しえますが、そこからの「判定」と「確定」ではそのうちのどれかひとつが選ばれるという図式になります。
理論を知らない人はここまで言語的に認知はできませんが、トーナリティの変化は感覚的に認知します(調性スキーマ)。しかし一方で、自分の「判定」がまだ「確定」していないことまでは当然知りえません。
私たちは、リスナーを正しい判定に導いてあげることもできれば、あえて誤った判定へと誘導し、そこから裏切りを行うこともできる。前者はリスナーにとって優しい作りであり、後者はインパクト重視、気持ち悪く聴こえる可能性もあるギャンブルです。それからもちろん、前方文脈による判定や特定音による判定をされないように意図的に避ける作りも考えられますね。
Check Point
多義性を帯びた和音が発生したとき、リスナーはその意味を「前方文脈」や「時間文脈」から「想定」する。情報が加わるにつれ選択肢が絞られていき、リスナーは意味を「判定」する。それは実際に音が鳴って「確定」するよりも先立って、文脈の力を借りて行われる。だからこそ、その判定を裏切ることも可能である。
作り手は、リスナーに何を「想定」させ、どのタイミングでどんな「判定」を下させ、いつ「確定」させるかをかなり任意にコントロールできるし、「確定させない」はもちろんのこと「判定させない」こともできるし、より複雑な音楽においては「想定」すらさせないこともできる。