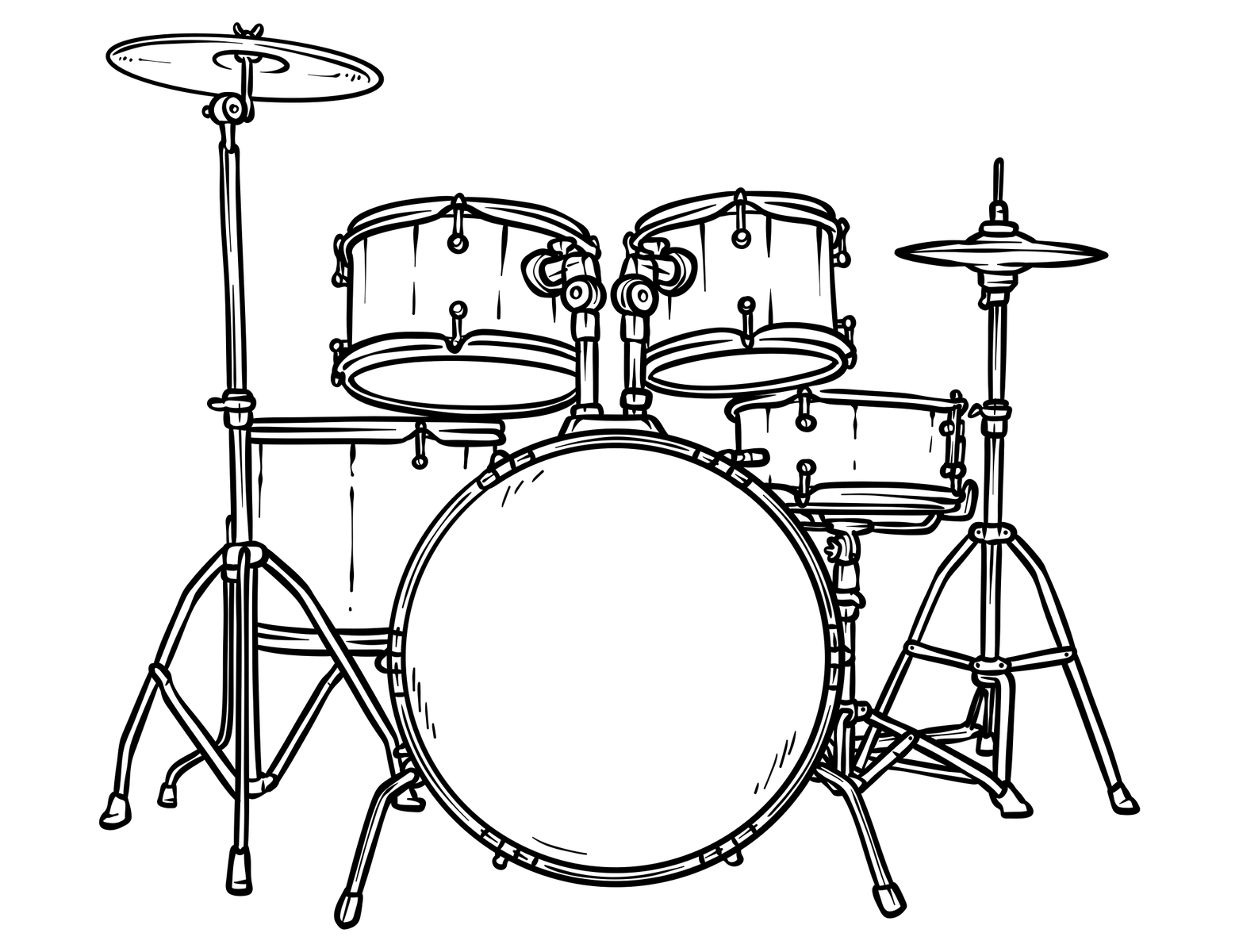目次
3. ドラムセットとリズム隊
リズム理論を進めて行く前に、準備編同様、まずは基本的なところを確認しておきます。
ドラムセットと3点セット
ポピュラー音楽のリズムを語るうえで欠かせないのが、ドラムセットDrum Set/Drum Kit/Drumsの存在です。
一人でたくさんの打楽器を、両手両足をフルに使って演奏するこの楽器セットは、ポピュラー音楽の多くのジャンルで楽曲のリズムを構成する中心的存在となっています。ドラムセットは19世紀後半から20世紀前半にかけて発展したもので、バッハやモーツァルトなどの古典クラシック音楽の時代にはもちろん存在せず、今でも基本的にクラシックはドラムセットを用いません。でも現代のポピュラー音楽においてのドラムセットの重要性はもはや語るまでもないでしょう。そのためこのリズム編でも、ドラムセットを前提とした解説が多くあるので、ドラムセットの基本について知っておいてもらう必要があります。
ドラムセットには太鼓やシンバルが多く並んでいる中でも主要なピースが3点あって、それがキック・スネア・ハイハットです。
それぞれ順番に紹介させてください。
キック
まず、リズムの最も低音部を支えるのがバスドラム、通称「キック」です。
この「ズン」という重たい響きは、文字通りリズムの“重み”をどこに置くのかを決定づける存在となっています。ドラムセットでは、右足で専用のペダルを踏んで演奏します。もともと吹奏楽では手でバチを使って叩いていたところを、足で叩くようになった。キックするから、キック・ドラムというわけです。
スネア
次にドラムセットでの主要な音となるのが「スネアドラム」です。スネアは明るくスコーンと抜けてくる非常に目立つ音であるため、スネアをどのタイミングで叩くかによって感じられるリズムは大きく変わってきます。
こんなふうに、合間合間に等間隔でスパーンと鳴らすのが、ポピュラー音楽でいちばん定番のリズムスタイルです。
ハイハット
最後に、シャンシャンと高い音でリズムに華を添えるのが、2枚のシンバルが重なってできている「ハイハット」です。しばしば「ハット」と略されます。
ハイハットは重みがなく軽やかなサウンドをしていて、弱く叩けば目立たないので、たいていの場合はキックやスネアよりも細かい刻みで演奏されます。ハイハットによってさらに細かなリズムの強弱ラインを提示することができるのです。ハイハットはスティックで叩くだけでなく左足のペダルを踏むことでも「シャン」という演奏ができ、また踏み方次第で音の長さを調節できる、とても繊細なパーツです。
もちろん実際の曲中では、キックを鳴らさないパートがあったり、スネアを叩かないパートがあったり、スネアがハンドクラップに替わったり、ハイハットがタンバリンに替わったりだとか色々ありますけども、ともかくこの3つがドラムセットの基本の3ピースとなっていて、この3つの楽器は俗に3点セットと呼ばれています。これについては、電子ドラムでも同じです。
- 色々な電子ドラムの3点セット演奏
どのような演奏が好まれるかは、ジャンルによって全く変わります。ですからリズムは本当にマネが大事で、自分がやりたいジャンルの作品をよく聴いてみましょう。その際は、まずはこの“3点”がどんな演奏をしているのかに注目すると分かりやすいと思います。
リズム隊
ことバンドの世界においては、ドラムとベースを合わせて「リズム隊」と呼ばれます。ベースも、キックと同じズシンとした低音を担う楽器なので、リズムに与える影響が大きいため、そのように言われます。
- 色々なベースラインのリズム
こんな感じで、たとえドラムが同じでも、そこにどんなベースが合わさるかによって印象が大きく変わります。もちろんウワモノの演奏も全体のリズムに影響を与えはしますが、やはり低音部が持つ影響力はひときわ大きいです。
4. リズムの定義?
専門用語があふれる音楽理論の世界の中で、「リズム」は珍しく音楽以外のフィールドでも普通に使われる日常用語です。聴覚刺激でなくても、ライトの点滅や振り子のふれといった視覚刺激、あるいは肩たたきのような触覚刺激にもリズムがあるし、もっと言えば地球の自転公転と月の満ち欠けなんかもリズムと呼ばれるものの一種ですね🌕🌗🌚🌓🌕
あまりにも当たり前の言葉すぎてスルーしていましたが、音楽における「リズム」の定義とは一体なんでしょうか? もちろん、定義とかはいいから実践的な話題に進みたいという方も多いでしょう。一方でそこが気になって先に進めないというタイプの方もいると思いますので、いちおう最後に定義をしておきます。
リズムを定義する
「リズム」という言葉を定義するのは案外難問で、辞書で「右」という言葉を定義するのに似た難しさがあります。簡単に言えば先ほど述べたように音楽をタテ(ピッチ軸)じゃなくヨコ(時間軸)で見たときの音のパターンなわけですが、もうちょっと正式に言葉にすると、さしずめこんな感じの言い方になるでしょうか……
- リズム (Rhythm)
- 時間軸上でみて周期性やまとまりといった何らかの秩序が見出せる、音の配置や長さ、強弱や高低などに関するパターン1。
リズムとはつまるところ、秩序のあるパターン。楽器の音じゃなくっても、演奏じゃなくっても、リズムになりえます。例えば公園にいるハトの「ホーホー、ホホー」という鳴き声が妙にリズミカルに聴こえてくることはありませんか? 注意して聴かなければ、それはただの環境音です。でも私たちがそこに何かの秩序を見出したとき、その音はリズムを持った存在となる。だからリズムの本体というのは実は音そのものではなくて、音の中に私たちが見出す法則にあります2。
- リズムを見出されたハトの鳴き声
別にドラムやシンセのような楽器音が無かったとしても、「ホーホー、ホホー」自体がすでに音楽的なリズム素材です。時計の針の「チクタク」という音の反復もそうですし3、なんならバスケットボールが床をバウンドする音なんかも、物理法則という“秩序”に従って生み出されていると捉えればリズムを有しているとも言えそうです。
ただこうなっていくと結局、どこまで不規則になっても“秩序”があると言えるかはものごとの捉え方しだいで、だんだん言葉遊びみたいになってきますよね。だから学者たちの間で議論しても話がまとまらない。そんな状況です。このサイトはあくまで実践重視なので、こうした純理論的な考察からはこの辺で手を引いておくこととします……。
ということで、改めてリズムを構成する基本的な要素をまとめると、次のような感じです。
- 周期やまとまり
- その中での打点の位置
- 各打点の強弱(アクセント)
- 音の長さや音量変化
- テンポの速さ
このリズム理論のテキストでは、リズムをどんな周期にするか、どこに打点を置くか、どんな強弱のアクセントをつけるか…そういったことを言語的にまとめていくことになります。
Continue