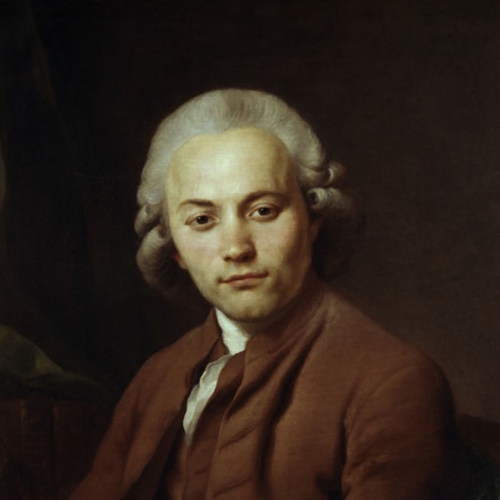目次
19世紀① : 崩されていく「型」
さて、“雇われの身”から解放されたことで、作曲家たちはオリジナリティーを発揮しやすくなりました。それに前世紀で基本の「型」が完成したこともあって、19世紀には逆に型破りな作品が次々に生み出されていきます。
“歌いやすく覚えやすい”が流行った時代がウソだったかのように、とにかく表現のクセがすごい。こうなったのには、市場の自由競争がさらに活発になったことで、個性的な作家が目立って生き残りやすかったという事情もあるようです1。
後を追う音楽理論
独創的な音楽が生まれる中で音楽理論界は何をしていたかというと、18世紀ほど劇的な変化を起こしてはいません。ただ決してノンビリしていたわけではなく、この時期は特にドイツの学者さんたちが理論をもっとシステマティックにするために頑張りました。
番号づけやグルーピング。いかにも理論らしいことをドイツの人たちがやってくれました。彼らが作ったシステムの恩恵を、現代の私たちも授かっています。しかし新時代の型破りな音楽たちを理論化するのは難しく、この時点ですでに理論と現実とでだいぶ差が開いています。
生理学・心理学の進歩
またそれとは別の大きな流れとして、19世紀後半ごろからは音楽への科学的な研究が広がりを見せます。もともと「弦の長さと振動」といった点から物理学とは深い関わりが続いていましたが、それだけでなく生理学や心理学といった学問からの研究が進んでいくのです。
音楽を論じるなら、鳴っている「音」だけじゃなくて、それを聴く「耳」、そしてそれを解釈する「脳」まで考えなきゃと。これは20世紀以降「音楽心理学」という一大分野となり、音楽理論に大きな影響を与えています。
19世紀② : 一方その頃アメリカ大陸
さて、西洋音楽理論の歴史を辿るメインの道はヨーロッパですが、ポピュラー音楽を構成している理論という点でいうと、アメリカ大陸から拾い上げておきたいピースがいくつかあるので、ここで寄り道をさせてください。
1776年に国家として独立したアメリカは、19世紀序盤イギリスとの戦争を経たのち、だんだんと自国の文化を発展させていくことになるのですが、19世紀半ばのアメリカ大衆音楽には、既にポップスの原型を見つけることができます。
スティーブン・フォスターはアメリカ音楽の父とも称される作曲家で、『やさしきネリー』は妻を亡くした黒人奴隷を歌ったバラードです。『大きな古時計』は、和訳版が日本でも有名ですよね。
ここで注目してほしいのはその楽曲構造で、まず『やさしきネリー』の方はシンプルなAメロが2回繰り返されて、そしてサビでタイトルを含んだ歌詞が登場して盛り上がるという形。そして『大きな古時計』の方は若干識別しづらいですが、まあAメロ2回→Bメロ→サビという風に見ていいでしょう。つまり、すっかり現代ポップスと同じ形式が出来上がっているんですね! 実はこのメロ-サビ形式がアメリカで定着したのが19世紀だといいます2。
こうしたポップス曲は先ほどの独創的なクラシック音楽と比べると普通に聴こえてしまいますが、よくよく考えたら現代の我々の感覚で聴いて“普通”と思えるって、それはまた違った意味でスゴいことです。だって彼らが確立したスタイルが200年経っても古びて廃れるどころか常識となって浸透し、当然のものになったということなのですから。
こうした曲のパート構成は「楽式」と呼ばれ、クラシックでも「ソナタ」「ロンド」など決まった形式がいくつかあります。言ってみれば、これも立派な音楽理論の一部です。この意味において、メロ-サビ形式を確立した19世紀アメリカのポップスも、音楽理論史を構成する重要なピースのひとつと言えるでしょう。
ラテンアメリカ系の音楽
また中南米およびカリブ海の方に目を向けると、やはり19世紀後半の段階でアルゼンチン/ウルグアイでタンゴだったり、また後のルンバやサルサの源流となるソンというジャンルがキューバで生まれています。
こうしたラテン系のジャンルは特にリズムの面で現代のポピュラー音楽に甚大な影響を与えています。このサイトの「リズム編」でもこういった南米のリズム理論を一部紹介しています。
南米とヨーロッパのミクスチャー
そしてもっと言えば、このようなラテンアメリカ系のリズムは当時のクラシック音楽にさえも影響を与えています。例えばフランスの作曲家ビゼーの「ハバネラ」で使われている特徴的なリズムは、キューバで19世紀に発展したハバネラという音楽スタイルを取り入れたものです。
同じリズムを使っているのが分かるでしょうか。 これは当時キューバを植民地支配していたスペインを経由してフランスまでスタイルが伝わったという流れがあるのですが、いわばロックバンドがレゲエのリズムを取り入れるようなジャンルの“ミクスチャー”がこんな昔にも行われていたわけなんですね。
世界は繋がっているのだから、ヨーロッパの音楽だからといってヨーロッパ以外の音楽が影響していないわけはない。今回のような歴史探訪はどうしても歴史のページを切り取りながら一直線に進むので、世界を単純に見せてしまいがちです。しかし本当の世界はもっとはるかに複雑に絡み合っていて、たくさんの“語られない主人公”たちによって今の豊かな音楽界が築かれているということは意識していてください。
それでは、もう一度大西洋を渡って、ヨーロッパへと視点を戻していきます🚢🌊
20世紀① : ルールからツールへ
さてクラシック音楽界では、20世紀に入ると“クセすご”もだんだん限界を迎えてきます。
こちらはロシアのストラヴィンスキーという作曲家によるバレエ音楽「春の祭典」ですが、まるで映画の緊迫のワンシーンでのBGMのようです。1913年にこのバレエが初公開された時には、音楽に加え振り付けや衣装の斬新さも相まって、現場の反応は大荒れだったといいます。
こちらは一聴した感じ、「今年の新しい日本茶のCMソングです」と言われたら納得しそうな、“和”を感じる一曲ですね。しかしこれは1903年にドビュッシーというフランスの作曲家が、東洋の音楽性を取り入れて作った曲(のオーケストラアレンジ)です。クラシックがそんなことをするなんて意外に思うかもしれませんが、前世紀でもうカリブの音楽とコラボしているのですから、それを思えば順当な流れにも見えます。
当然こういった前衛性や民族性を盛り込んだ楽曲には、古典派理論に反するような音使いも含まれています。楽器こそクラシックだけれども、その中身を見れば現代のポピュラー音楽と全く変わらないようなチャレンジが、実は20世紀の初めですでに開拓されていたのです。
そして前衛芸術へ…
20世紀初頭の時点で既にやれそうなことをドンドンやり尽くしていき、やがて芸術としての進化に限界を感じた作曲家たちは、既存の枠組みを完全に捨てて根本から新しい型の音楽を作りはじめました。
![]() ペンデレツキ “広島の犠牲者に捧げる哀歌” (1960)
ペンデレツキ “広島の犠牲者に捧げる哀歌” (1960)
全く聴き馴染みのないような音使いに、とても想像できないような展開の連続。もちろんこれはデタラメに作っているのではなく、従来とは全く異なる新しい音楽を創造するためにあえて前衛的な技法を自分たちの手で理論立てて、意図的に既存の音楽から脱却した結果です。だいたい1910年頃からこのような作品が現れはじめ、世紀の前半のあいだにクラシック界の中ではかなり大きなムーブメントとなりました。
「作りたい音楽のために、まずオリジナルの理論を作った」というのが面白いですね。気がつけば、理論はルールじゃなくツールになっていたのです。古典的な曲を作りたければ古典派理論を使うし、斬新な曲を作りたければ新理論を使う。それはモンスターハントのゲームで敵に合わせて武器を持ち替えるのと同じことで、20世紀の人にとったらそれくらいもう当たり前のことでした。
理論の歴史は、創造と破壊の歴史
さて、理論を誰かが作っては誰かが壊して、作っては壊してを繰り返してきたというなかなかショッキングな歴史がありました。
ここから分かる大切なことがいくつかあります。まず、アーティストはいつの時代も理論にない新しい音にチャレンジしてきた歴史があるということ。斬新な音楽は必ず批判を浴びたこと。でも最終的には理論もそれを受け入れて変化してきたこと。「理論」というと、もっと人為の入り込む余地のない合理的なものをイメージしていたかもしれません。でも基本的に音楽理論というのはまず現実の音楽ありきで始まり、そこから統計的というか、経験論的に構築されていったものなのです。
このプロセスに関しては、言語と文法の関係性にそっくりです。まず言語があって、それに合わせて文法体系を作るんだけども、人々の言葉使いが変わっていくにつれ文法もまた再考しなきゃいけなくなる。そういうサイクルを、音楽と音楽理論の世界も繰り返しています。
そして理論はあくまで「基本の型」でしかないのだから、それを破ることは何ら問題ではない。それはクラシックの歴史自身が証明していることなのです。
とはいえ、彼らは従来の型をしっかり勉強したうえでの計算された“型破り”なのだから、私たちもその型をちゃんと学ぶべきなのか? という疑問はあるかと思います。これに答えるには、まずこの歴史の続きを見ていく必要があります…。