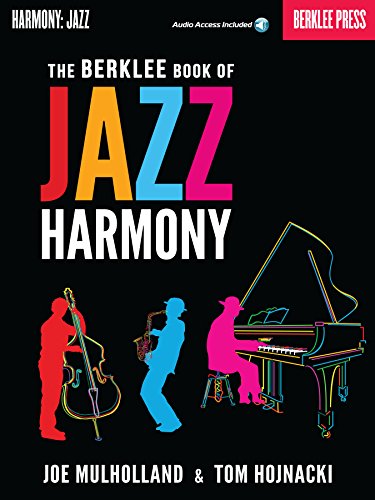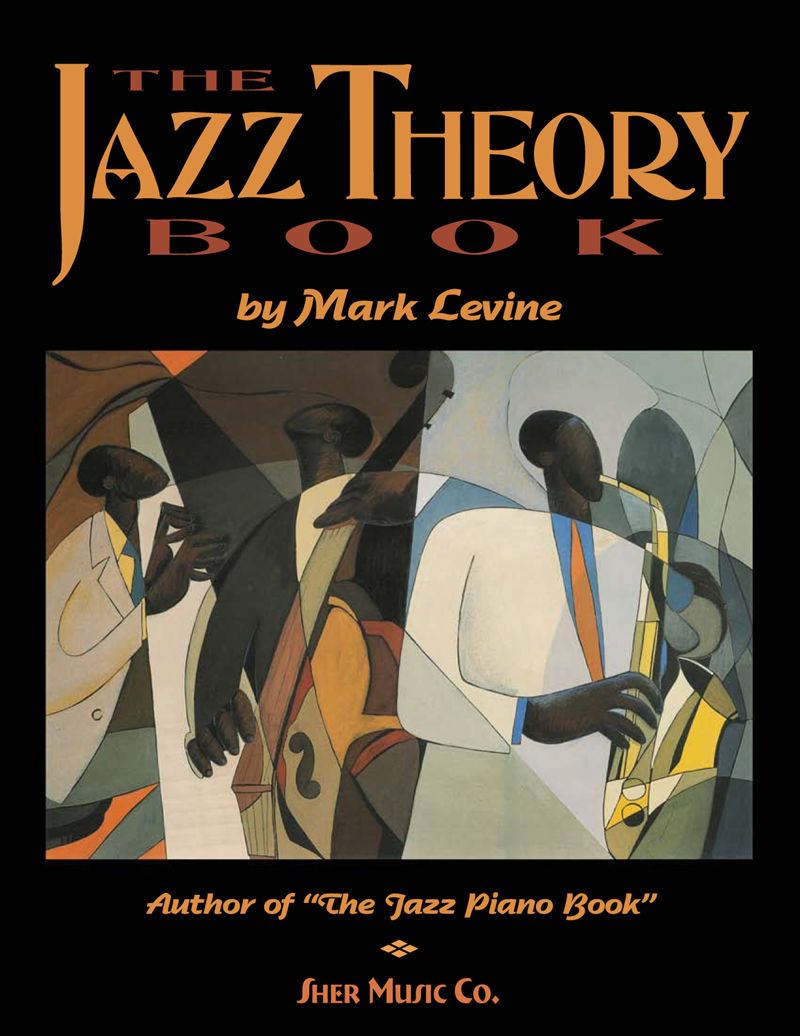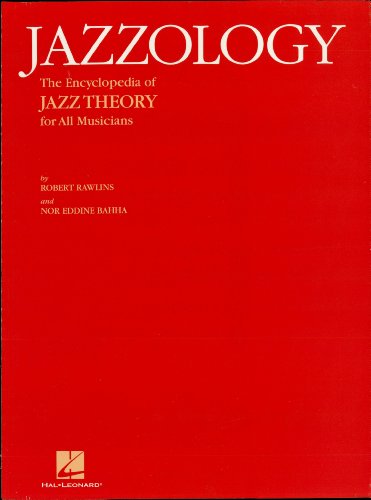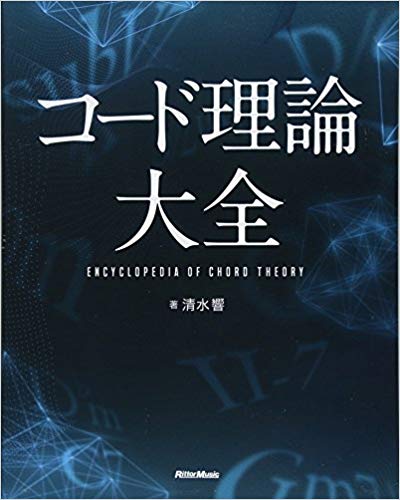目次
さて、いよいよコードスケール理論(CST)を用いた実践を行います。当然本来的にはジャズでこれを行うわけですが、せっかくなので今回は、ジャズ以外のジャンルで実践をします。
「ジャズ理論の、ジャズでの実践例」だったら、ジャズ理論書なりなんなりでいくらでも見つけられるわけなので、ここはポピュラー音楽への応用法を伝えるのが自由派の役目だろうという判断です。
1. モード・チェンジ
覚えた27個のモードを活用する最たる方法が、同じルート上でモードを変更することです。 この章の中盤では、III7のコード上でいくつかスケールを交換するパターンを紹介しましたね。あの時はまだコードスケール理論がなかったので、やや表面的な説明にとどまりました。それを深掘りするのが今回ということです。
ルート基準のモード交換
モードを交換するといえば、この章の序盤でやった「モーダル・インターチェンジ」という用語が思い浮かびますよね。でもあれはまだCSTを知る前の話で、交換するのもキー全体を統括する、いわゆる「親」のスケールの交換でした。
ご覧のとおり、交換の軸はキーの中心でした。上の例ではキーがCメジャーなので、「C 〇〇 scale」で常に交換している。これは言ってみれば、キーに依存した方法論ですね。しかしCSTの醍醐味は、コードをキーから切り離して考えること。キーの制約から自由になれることなのですから、モードの交換においてもいちいちトーナル・センターを基準にして考えるやり方は、ちょっとポリシーに反しています。
だから今回は、各モードの中心の音(モード・ルートと呼ぶことにします)を軸にした交換を考えます。
このように、CSTのシステムに基づいて1つ1つのコードに分解してから、モードを交換します。キー非依存のモード交換を行うのです。
名前について
この「1コード単位のモード変換」については、実は取り立てて名前がついていません。ようは「候補のコードスケールから一つを選ぶ」という行為なので、あまりにも日常的な行為だからかもしれませんね。
いちおう広義の「モーダル・インターチェンジ」の一種と言えそうですが、しかし微妙にやっている内容が異なるので、同じ言葉をあててしまうと逆に紛らわしそうです。ここでは便宜的に、モードを交換するということで、単に「モード交換Mode Change/モード・チェンジ」と呼ぶことにします。
- モード・チェンジ
曲中のあるモードを、同じモード・ルートを持つ別のモードに置き換えること。
これも言うなれば「クオリティ・チェンジ」の順当なアップグレード版です。I章の時にはコードクオリティの変化だけに着目し、「メロディを作る時には、他の音もつられて変化したりもします」なんていう茫洋とした話で終わっていましたね。
それをキッチリ理論化し、さらには「クオリティは変えずにテンションだけすり替えることも出来る」という「ノー・クオリティチェンジ、イエス・モードチェンジ」のエリアにまでメスを入れていくわけです。
この記事の続きを読むには、ログインが必要です。サイドバーのログインフォームからログインしてください。メンバー登録は無料で可能です。
モードの交換は自由
大前提として、モードの交換に決まったメソッドはありません。基本的にジャズ理論が教えてくれるのは、何かが「Available(利用可能)」であるというところまでなので、Availableである候補たちをどのように選択するかというのは、理論の使い手に委ねられています。
ここではいくつかのシチュエーションを想定して、知識をどのように実践に結びつけていくかの実践例を紹介します。
2. VI-7でモード・チェンジ
まずは、同一コードクオリティ内でのモード・チェンジ。例えばダークな雰囲気のBGMで、VI–7一発でしばらく進むような音楽を考えます。
- VI Dorian
こちらはドリアンモードで演奏した例。ちょっと、全体のダークな雰囲気からすると、ドリアンは明るすぎて微妙です。そこで今度は、暗めのフリジアンにしてみます。
- VI Phrygian
そうすると、重苦しさは出ましたが、ちょっと重すぎて、「張り詰めた緊張」みたいな情感がなくなってしまいました。これもちょっとしっくり来ない・・・。こんなとき、CSTを知らなかった頃は「じゃあやっぱり普通のマイナースケール(エオリアン)か・・・なんか普通に収まっちゃったな・・・(´・ω・`)」とションボリするしかありません。
しかし! 27個のモードを網羅した今なら、すぐにある事実に気づきます。ドリアンとフリジアンの間くらいがいいのなら、ドリアン ♭2を使えばいいのだ。
ご覧のとおり、「モードマップ」上では、ドリアンとフリジアンのちょうど中間地点にいるのは、「ドリアン ♭2」。モードの世界をじっくり探求してきたからこそ、この可能性をすぐ発見できます。「クリアな思考」で、音楽世界を見つめることができているのです。さっそくドリアン♭2でフレーズを作り直してみます。
- VI Dorian ♭2
お聴きのとおり、ドリアン特有の明るい6thと、フリジアン特有の沈んだ♭2nd。両方が混ざり合って、実にユニークなサウンドを生んでいます。
「ドリアとフリジアを混ぜてドリジア旋法や〜」は、メロディ編の「音階の調合」でもやりました。あの時は試行錯誤でやっていたことを、最初から知識でカバーしてしまう。まさに“順当な体系のアップグレード”をいま実行しているのです。
3. Root VIでモード・チェンジ
今度はコードクオリティ基準じゃなく、ベース音とメロを固定した状態でモードを交換するパターンもやってみます。
- ルートがVI、メロが9th
例えばこんな風に、VIがルートで、メロに9thの音を鳴らし続けて、やっぱりダークなBGMを作ってみるとします。「コードの内側を色々変えることで、メロの9thの聴かせ方を変えていく」という方法で曲を彩っていくわけです。
VI-7を司るモードである「エオリアン」のすぐ下には「エオリアン ♭5」がいますから、まずそこへ移って、コードクオリティをさっそくハーフディミニッシュに変えてみましょう。
そしてここから二段階明るくして、マイナーメジャーセブンスのエリアである「ハーモニックマイナー」に進んでみる。ちょっと冒険です。
4小節目はこの「ハーモニックマイナー」のまま、あえてアヴォイドの♭6thを思いっきり鳴らして、解決への欲求を高めてまた「エオリアン」へ帰還しようと思います。
- エオリアン→エオリアン ♭5 →ハモマイ×2
5thや7thのあたりでコードクオリティに変化をつけていますが、最重要であるRtと3rdは一定、さらにメロの9thも一定なので、自然な音響変化に留まっています。ルートがVIのときに、ハーフディミニッシュやマイナーメジャーセブンスを使う。これもセンスだけではなかなか実行する勇気の持てないところですよね。
このような「メロディ・オーダーのハーモナイズ」は、メロディ編V章で扱ってきたことです。あちらでは原理や原則から理論化をしましたね。こちらは個体のデータを集めて暗記するという真逆のアプローチ。両者を噛み合わせることで、より強力なメソッドとなるでしょう。
こんな風に、「スケールから音楽の展開を考えていく」なんてやり方は、ポピュラー向けのライトな音楽理論の範囲では扱っていないメソッドです。CSTを学ぶことで、このような音楽の構築法が可能になり、創造性はいっそう自由になれるのです。
4. V7でモード・チェンジ
メロ先行で、歌モノに伴奏をつけるパターンなんかもやってみましょう。おなじみIVΔIII7VI–7V–7のコード進行でメロを考えたとします。
- IVΔIII7VI–7V–7?
サックスが仮メロです。いい感じにできたかな? と思いきや、ある問題に気づきます。このメロディ、V-7のところでシ♮を思いっきり歌っているのです。
このままでは、V-7のコードトーンであるシ♭とガンガンにぶつかって、綺麗にサウンドさせられません。
- 最後にむりやりV–7
このとおり、高らかに歌いたいシ♮のメロと、切なさを出したいシ♭の伴奏が競合して、魅力が相殺されてしまいます。困りました。かといって、代替案で単なるVとかIΔとかでは、ちょっと単調です。「シソミ」というメロから思いつくコードなら、VI7なんかがありますが・・・
- 最後にVI7
サウンドは悪くないけど、ルートの動きがVI続きで、ちょっと展開性に欠けますね・・・。やっぱりルートはVに行きたいのである。そうなると万事休す、早くもネタ切れです。こうやって、メロからのリハーモナイズを考えるとき、ポピュラー理論の範囲では意外と選択肢が狭いんですね。そこで、コードスケール理論の出番。
メロは「シソミレソ」ですから、Vをルートとすると「Rt・M3rd・P5th・M6th」が確定している状態です。ここに何かピッタリはまるものはないだろうか?そこでモードの世界に思いを巡らせると・・・
そうだ! リディアン・ドミナントあたりが適任ではないか? と、すぐに候補が浮かんできます。♯11のサウンドはVI7と似たところがあるから大人っぽくて良い感じだし、構成音もメロにうまくはまる。
- 最後にV Lydian Dominant
ちゃんとルートはV、メロも生きていて、それでいてサウンドにも毒がある! 自分の表現したいものを素早く適切に形にできました。きっと、CSTの知識がなくても、じっくり考えればこのような音を閃くことはできるでしょう。しかし、これを見つけるまでのスピード、モードごとのキャラクターに対する深い理解。CSTのおかげで、あらゆる作業がスムーズになります。
コードスケール理論は、確かに即興演奏をいちばんの目的として考えられたシステムですが、こうやって制作においても、自分の思い描くサウンドを具現化する手助けをしてくれるのです。
コードクオリティを固定した交換、ルートとテンションを固定した交換、メロとルートを固定した交換。まあ主な交換パターンは、この辺りだと思います。ただもちろん他にもこのモードの考えを活用できる場面はたくさんあるでしょう。転調の方法論に発展させたり、多調性の音楽を構築する際の参考にしたりね。
このマップ自体が、インスピレーションの源泉と言えるかもしれません。たった9回の「コードスケール理論」でしたが、スケールから音楽を捉えていくジャズ系理論の魅力が垣間見えたのではないでしょうか。
本格ジャズ理論書の内容
さて、この章で紹介できたのはジャズ系理論のおおよその枠組みと特色、ポピュラー音楽で活用できる基本的なスケール等のみです。実際の分厚い書籍を手に取ると、例えば以下のような情報が豊富に載っています。
- 各コードに対応したコードスケール
- より多くのヴォイシングのサンプル
- さらに多くのスケール
- 実際のジャズプレイヤーの「アウトサイド」な演奏例
後半では「コードスケール理論」の考え方を理解するのに相当な量を割きましたが、これはジャズ理論の基本であって、中心ではない。また「ジャズ系理論」といってもその中身はまたそれぞれ異なっていることには注意してください。色々と学んだ今改めて、この章の冒頭で紹介した参考文献たちの特徴を紹介します。
「The Berklee Book of Jazz Harmony」と「The Chord Scale Theory & Jazz Harmony」はいわゆる「バークリーメソッド」と呼ばれる、バークリー音楽大学流の理論体系がしっかりと学べる洋書。記述が細かく、正統な「バークリー流」が学べるという点で安心感があります。ただどちらも「辞書的構成」ではなく「学習書的構成」の色が強いため、「気になることがあった時に、辞書のようにサッと引く」という用途には向いていません。どっしり腰を据えて、練習・実践と並行しながらレベルアップしていくタイプの書籍だと思います。
「The Jazz Theory」は、バークリー派とは幾分コンセプトが異なり、この本には、TDSの機能の話も出てこないし、「モーダル・インターチェンジ」という言葉も出てこない。代わりに実際のジャズ曲からの楽譜の引用が非常に豊富で、ジャズに必要なことだけに特化した「純ジャズ理論」とでも呼ぶべき形式になっています。「システム」や「メソッド」を読者に植え付けるというよりは、ジャズプレイヤーとして成長することを第一の目的に作られた本という感じがします。思想的側面がよく学べるのが魅力。
「Jazzology」は、クラシック的見地など他流派との繋がりを残した状態で、バランスを保ちつつ書かれたような印象があります。他流派を学習済みの人間がまずジャズ理論に触れるに際しては分かりやすい一方、良くも悪くも中立的で、ジャズの思想に深入りはしていない印象です。
「コード理論大全」はバークリー系列のコード理論が丁寧に解説された和書で、“体系的にまとめる”という意志が強く感じられる一冊です。先ほどの洋書2つと違い、前半は完全にCST抜きで解説し、終盤にCSTを紹介するという分離構成になっているため、「辞書的」な使用をする場合には他の書籍に比べ使いやすいです。内容は完全にバークリー系列なのですが、「ジャズ理論」とは一切銘打っていないので、ジャズ主体の見地にたった記述は基本的になく、あくまでもニュートラルな立場で書かれています。
豊富なスケールやヴォイシングの知識は、特に映画音楽やゲーム音楽といったBGMの制作において非常に強力な武器になりますし、もちろんソロフレーズの幅を広げることもできます。やはり根っこが演奏の理論ですから、それにまつわる情報量が非常に膨大です。よりジャズの世界にのめり込みたい方は、読んでみると良いでしょう。