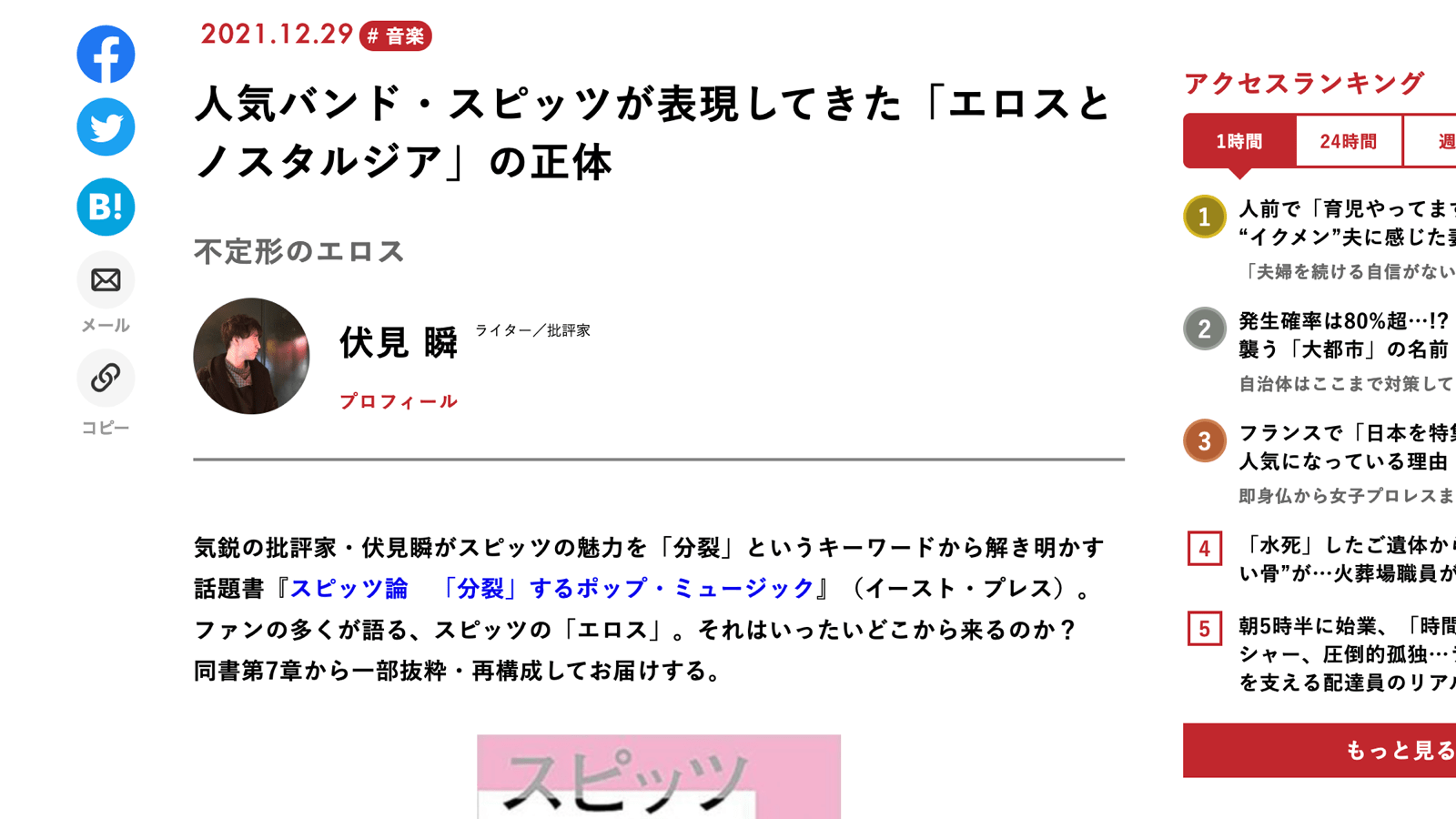目次
伏見瞬さん著作の『スピッツ論 「分裂」するポップ・ミュージック』という書籍が刊行されました。
- スピッツ論 「分裂」するポップ・ミュージック
- Amazonで見る
“なぜ、スピッツはこれほどまでに愛されるのか?
ポップでマニアック、優しく恐ろしく、爽やかにエロティック。
稀代のバンドの魅力を「分裂」というキーワードで読み解く画期的論考。”【目次】
第1章 密やかさについて ─ “個人”と“社会”
第2章 コミュニケーションについて ─ “有名”と“無名”
第3章 サウンドについて ─ “とげ”と“まる”
第4章 メロディについて ─ “反復”と“変化”
第5章 国について ─ “日本”と“アメリカ”
第6章 居場所について ─ “中心”と“周縁”
第7章 性について ─ “エロス”と“ノスタルジア”
第8章 憧れについて ─ “人間”と“野生”
第9章 揺動(グルーヴ)について ─ “生”と“死”
そして私はこの本の音楽理論に関する記述の校閲として関わりました。より具体的には、異名同音の綴りや流派によって語義がぶれる言葉への配慮、またスピッツの楽曲分析に関して(コードネームなどに)ミスがないかといった確認などです。
それで、出版業界と何の縁もゆかりもない私が呼ばれたのには理由があります。それは、この本で当サイトの「メロディ編」で提唱している「調性引力論」が利用されているからです!なのでこの記事では、その辺りの話も含めながら、この本の紹介をいたします。
このサイトで音楽理論を学んだという方と、そうでなく単にスピッツが好きという方、どちらともに向けて本の概要を説明していきたいと思います。
1.『スピッツ論』の特徴
『スピッツ論』はその名のとおり、スピッツを“論じる”本です。それというのはつまり、単にスピッツの歴史を述べた「スピッツ史」でもなければ、単にスピッツ自身の言動を記録した「スピッツ録」でもなく、またスピッツの作品をレビューしていくだけの「スピッツ評」でもないということです。
もちろんそうした歴史・記録に関する面も情報として取り上げられていますが、主軸はスピッツに対する論考です。では論考とはどういうものなのか? さいわい「第3章 サウンドについて」「第7章 性について」の一部を抜粋・再構成したネット記事があるので、ちょっと興味あるぞという方はぜひ試し読みをしてみてください。
この二記事だけでも見てとれますが、他アーティストとの比較、他文学との比較、フレーズの分析、歌詞の考察…など、章ごとに異なるさまざまな観点からスピッツを論じているというのが、この本の特色です。
クロノロジカル(時系列順)で話をしていくのではなく、「分裂」というテーマが骨としてあり、スピッツの歴史を何周もぐるぐるしながらその骨に肉をつけていくという構成です。そういった点で、オムニバスやアンソロジーめいた楽しさのある一冊です。
イメージとしては、「スピッツ分析シンポジウム」が開催されて、各分野の専門家がやってきて各々の説を述べあうというような、そんな構図に近いものがあると思います。
「分裂」というワード自体は解釈の幅が広くあるため、「分裂といっても、こんな分裂もあるぞゥ」という感じで、次々に引き出しが開いていくわけですね。逆に言うと、話題は多岐に渡るんですけども、みな「分裂」というキーワードになぞらえて論じられるので、どこか軸足が動かないような安心感を持って読み進められます。
スピッツを切り取る“切り口”の手数が多いため、どんな人が読んだとしても「そういう見方もあるんだぁ」という発見があるはずです。
「ポップ・ミュージック」について
スピッツファンの方においては、本書がサブタイトルに「ポップ」という言葉を冠していることに対して抵抗感を覚えるかもしれません。
なのでここは弁護をしておくと、音楽における「ポップ」という言葉は、必ずしも「ロック」の対義語として用いられるものではありません。
もっとずっと広い意味、クラシック音楽や民族音楽なんかとの対比だったりで、産業音楽全般をさして「ポップ・ミュージック」と称するようなことはときどきあります。本書における「ポップ・ミュージック」の定義については序文で説明がされていて、その全文もまたウェブ上で読むことができます。
ですから、このサブタイトルをもってスピッツへの理解度を訝しむのであればそれは杞憂です。例えば「第7章 性について」で最も文章量を割いて解説されている曲は、〈ナイフ〉です。p.192-199までずっと〈ナイフ〉の話をしてます。
しかも、歌詞の話だけではありません。この間奏パートの演奏なんかについても詳細にレビューされています。200曲以上ある中から選んだのが〈ナイフ〉!これ以上の説明は不要でしょう。
2. 「調性引力論」による分析
上で紹介した2つの抜粋記事では一般リスナー向けに読みやすい箇所が選出されていますが、全体を見渡すとメロディ・コード・リズムのそれぞれについて音楽理論的な分析を試みている箇所が端々にあります。
そして主に第4章と第8章で、楽曲のメロディ分析に際して「カーネル/シェル」の概念が実際に用いられています!㊗️ 🎉
当然まだ一般的な用語ではないので、わざわざ簡潔に定義の説明をして、読者に概念を導入したうえで使用してくださっています。
まず説明に紙幅を割かなきゃならない、そして文面だけの説明で理解してもらえるか分からない。しかも紙の本には載っていない、いちウェブサイトの唱える言葉である。そういったリスクを負ってまで理論を採用してくださったということに感謝です。それと同時に、そうしてまで使いたいと思ってもらえたという話でもあるので、たいへん嬉しくもあります。
主な分析対象となっている曲は〈愛のことば〉〈楓〉〈フェイクファー〉です。特に〈愛のことば〉の方では、なんとギターフレーズの音選びまでカーネル論で分析しています。具体的にどの音を取っていてどんな効果をもたらしているかを論じていて、かなり読み応えのあるパートになっています!
アルペジオがテッちゃんのプレイのカギであることは誰しもが知っている。でも単にコードトーンを分散するだけでは“あの演奏”にはなりません。音楽的にどんなことをしているのか? その一端を知ることができます。
ギターソロの分析もあって、〈愛のことば〉のソロが何の音から始まって何の音で終わるか、それが表現上どんな意味を持つのかまで論じています。
カーネル/シェル論の大きな意義のひとつが、決して音楽的に複雑でないのに魅力的な音楽があったとき、それを分析するためのモノサシを提供することです。スピッツの音楽はまさにその最たる例と言えます。だから今回は果たすべき役割を果たさせてもらえたなという感じで、しかもそれが大好きなスピッツの曲でとは、本当に感無量です。
〈愛のことば〉に関して
ところで本書の114ページでは『〈愛のことば〉のBメロとCメロの歌が同型リズムであることも、私は「SoundQuest」から教わった。』とあります。これはメロディ編I章の「モチーフ」の記事に書かれていた内容なのですが、以前に記事を改訂した際に〈愛のことば〉は選曲からもれて、この記述はなくなってしまいました。もし〈愛のことば〉の解説を探し回っている人がいたらごめんなさい(°-°)
3. 作り手と『スピッツ論』
『スピッツ論』のユニークな点のひとつとして、これがリスナーだけでなく音楽を作る側の人間も視野に入れて書かれているというところがあります。序文にて「音楽をつくりたい人が具体的に参照できる本であることも目指す」というモットーが明示的に表明されているのです。
「具体的に参照」となると、やっぱり理論的分析がカギになってきます。だから「調性引力論」以外にも理論を用いた考察は充実していて、例えばスピッツの音楽に漂う「情けなさ」がどこから来るのかを音楽理論的に説明しようとする箇所なんかもあります。
「情けなさ」がスピッツを評するうえで重要なキーワードのひとつであることは、スピッツファンなら誰しもが頷くところ。
その要因となるものを、歌詞だけでなくリズムやコードの面から、いくつかの曲を例にとって探っています。ほか第9章では﨑ちゃんのドラムの特徴について理論的に解剖していて、そこではジャズやヒップホップとの類似性が、これもまた具体的な形で指摘されています。
なかなか詳細に再現性のある形で情報が提示されているので、スピッツの音楽性の中身を知りたいという人には価値ある情報が色々と見つかるはずです。
4. 聴き手と『スピッツ論』
ここまで理論に関わるパートばかりを取り上げてきましたが、全体を見れば理論を使わずに一般的な言葉で論じる場面の方が多くあります。歌詞解釈もたくさん載っていますし、社会や歴史を交えた評論もあります。
第2章 コミュニケーションについて
特徴的なのは、第2章にある《おるたな》のレビューです。一部を引用すると……
《おるたな》に収録されているほとんどの曲は2011年以前に録音されたものだが、どこか3・11に対する応答のように感じられる。 (中略) 《おるたな》で示した音の荒々しさは、東日本大震災と福島第一原子力発電所で明るみになった、日本社会の偽善と隠蔽体質へのアンチテーゼとして響く。
伏見瞬『スピッツ論 「分裂」するポップ・ミュージック』p.66-67
ここは楽曲分析とは対照的なアプローチで、社会的コンテクストからスピッツの音を論じています。〈オケラ〉のイントロのドラムを聴いたスピッツファンはみな過去最大級の迫力に震え上がったわけですが、それをここでは震災と結びつけて寸評することを選んでいます。
「震災前にRECした曲でも、震災後にアルバムに再収録したからこの音は震災へのメッセージ」という論理は、かなりコンテクスト優位な論じ方ですよね。
理論による楽曲分析をいくぶん客観性の高い評論と位置付けるならば、こうしたコンテクストからの論評というのは解釈の自由度が大きく増す分、主観性の強い評論と言えます。180°異なる語り口が、一冊の中に共存しているんですね。私個人としてはこのタイプの論評は好みでないですが、逆にこういうのがあってこそ評論だという人もいるでしょう。
第5章 国について
ほか、「第5章 国について」ではスピッツと日本語ロックについての考察がなされます。マサムネさんは日本語詞にこだわりがあって、英単語を用いたタイトルはこれまでに「HOLIDAY」はじめ数曲しかない。英語の詞も数えるほどしかない。ここはやっぱりファンとしては掘り下げてほしいところですよね。
日本語ロックの話といったらビートルズ以降の「日本語ロック論争」の文脈が定番としてありますが、この本はココに関して気合の入れ具合が違います。ちょっと象徴的な一節をまた引用させていただきます。
1853年7月8日、アメリカ合衆国ロードアイランド州ニューポート出身の縮れ毛の男が率いる4隻の艦隊が浦賀に来航して以来、日本の政治組織は西洋の力を意識せざるをえなくなったことは誰もが知るとおりだ。
伏見瞬『スピッツ論 「分裂」するポップ・ミュージック』p.134
「縮れ毛の男」とは、ご存知ペリーのこと。なんと、ほんとうに「日本語」と「アメリカの音楽」が公的に交わりはじめた最初期にまでさかのぼって話が展開されるのです。西洋音楽の様式が日本に受容されていく過程を読者と共有したうえで、スピッツの音楽に感じる“懐かしさ”のようなものの根源を探ろうとします。
確かにスピッツには、特に初期スピッツには異様な日本らしさというか、アメリカンなロックからはかけ離れたような音楽性を感じるときがありますよね。
この何とも言い難いスピッツの独特さを、西洋と日本という“分裂”から論じています。
第6章 居場所について
スピッツに限らずロック好きの方が特に楽しめるのが、「第6章 居場所について」だと思います。ここでは、スピッツと同世代のアーティストがどんな音楽をしていて、それぞれ誰の影響を受けている/受けていないかといった、ロック音楽史の視点からスピッツの立ち位置が説明されます。
例えばスピッツと比較されることの多いミスチルはずばり「Tomorrow Never Knows」というタイトルの曲があったり、歌詞に「Ticket To Ride」という言葉が出てきたりして、ビートルズからの影響を隠さずむしろ露骨に出しています。フレーズにもオマージュが見られたりして、そのことは本書でも指摘されます。
ではひるがえってスピッツはどうなのか? ビートルズの影響はあるのか。ないとすれば、では誰の音楽との類似性が見られるのか。邦楽洋楽問わずロックバンドの名前がたくさん飛び出すこの章は、ロックファンがワクワクしながら読めるセクションだと思います。
そんなわけで、この記事で紹介した内容だけを見ても、社会との関係を論じる2章、サウンドの変遷を追う3章、メロディを理論的に解剖する4章、日本語ロックのルーツを辿る5章、J-Rock音楽史を俯瞰する6章、スピッツのエロスを考察する7章……と実に色とりどりの内容が含まれています。
『スピッツ論』というタイトルを耳にしたとき皆おのおのがイメージした“スピッツ論”の内容というのがあると思うんですが、それぞれが想う「この話が入ってなきゃ私の中で“スピッツ論”とは言えないぞ」という論点が、おおよそ全部詰まっていると思います。
長年スピッツファンやってきましたが、「あの話題に触れてくれてもよかったのにな」という不満がほとんど思いつきません。強いて言うならギター等の機材の話を掘っていないのが一部のバンドマンには寂しいかな? くらいでしょうか。それでも著者一人でここまで網羅したことを考えれば、このボリュームは十分すぎます。
スピッツの最初の評論本が、このようにインクルーシブ(包括的・非排他的)なものでよかったと深く思います。正直なところ私自身は、他人がする文芸評論や歌詞解釈に興味はありません。それでも、客観的なデータ・記録や音楽内容を深掘りする章があったので楽しめました。逆に音楽理論的な部分に興味のない人は、私とは正反対の楽しみ方をすると思います。そういった意味で、この本を読んだ人どうしで「あの本好きだった?」ではなく「どの章が好きだった?」という形でワイワイ話し合える本です。
「他人がスピッツのことを論じるのを聞きたくない」という人にはさすがにおすすめできませんが、そうでなければ、新しい知見が得られると思うので、スピッツファンなら持っておいて損のない一冊だと思います。