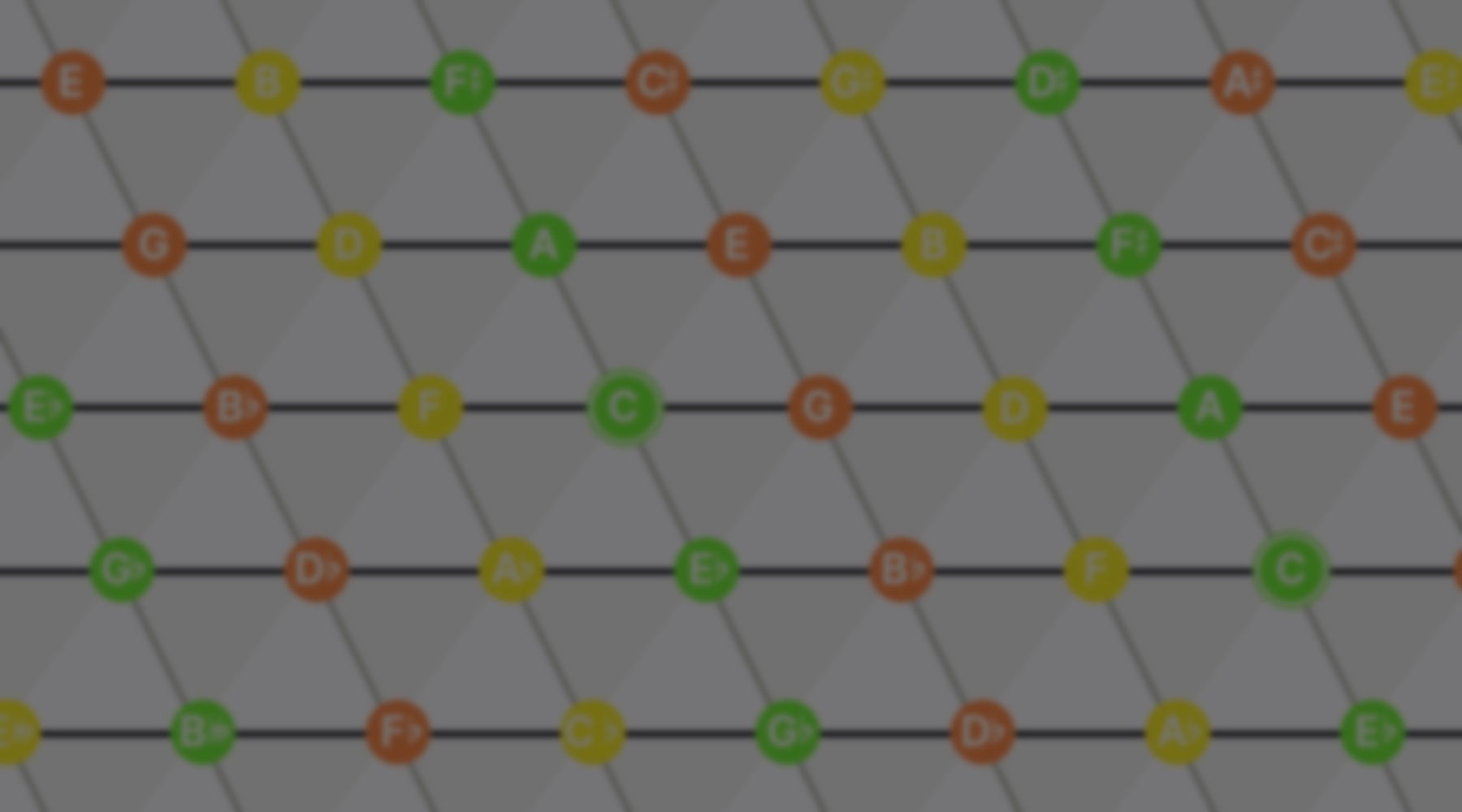目次
前回の機能和声の変遷❷の記事の中で、リーマンにインスパイアされた(主にはアメリカの)理論家たちが、リーマンのアイデアをある程度継承した理論を発展させたという話をしました。そうした理論的研究を総称してネオ・リーマン理論Neo-Riemannian Theoryといいます。この分野は21世紀に入った今でもまだ盛んに議論が進んでいて、現在進行形で発展中の理論です。
この記事では、ネオ・リーマン理論と呼ばれる研究の中から主要なものを紹介していきます。
1. 変形の理論
まず機能和声の変遷❶で説明したとおり、リーマンは数々のコードに対しTDSいずれかとのコードとの関連性をもとにしたシンボルを与えていきました。
特徴的なのは、ご覧のようにCmもAmもEmもCを1音ずらしたものという、“ずらし”によって和音を説明した点です。リーマンの理論はそのような変形操作によって出来た和音に対し固有のシンボルを与えるというもので、彼がやろうとしたのはローマ数字記法に変わるコードシンボル体系の構築でした。
しかしネオ・リーマン理論はこの点に関して異を唱えます。ずらしというアイデアが面白いのだから、RelativeだとかLeadingtone-changeだとかいった言葉は和音の名称とするのではなく、ずらすという操作(operation)の名称として使った方がよいと考えたのです。ネオ・リーマン理論の先駆者であるデビッド・ルーウィンは、リーマンが和音を変形させるアイデアを展開していながらも「変形の理論」としてそれを打ち出しはしなかったことに関して、かなりけちょんけちょんに批判しています。
An even more basic problem for Riemann was that he never quite worked through in his own mind the transformational character of his theories. He did not quite ever realize that he was conceiving “dominant” (whether DOM or DOM′) as something one does to a Klang, to obtain another Klang. Here, I conjecture, he was unduly influenced by a desire to promote his notation as a substitute for Roman-Numeral notation;
リーマンのもっと根本的な問題は、彼が自分の理論の持つ変形理論的な性質について彼自身でも理解しきれていなかったことです。彼は自分自身が「ドミナント」をある和音から別の和音を得るためにする行為だと着想している自覚が全然ありませんでした。ここで推測しますが、彼は自分の記法をローマ数字記法に成り代わる存在として売り出すという野望に闇雲に駆られていたのでしょう。Lewin, David. Generalized Musical Intervals and Transformations (p.177).
当時の野心までもをディスられて、かわいそうなくらいの言われようです。しかし同様のディスは他の論者からもなされていて1、確かに以前の機能和声論の記事中でもリーマンのFunctionは和音を別の和音に変化させるプロセスを表した“計算式”のような側面、関数っぽさがあるという話が登場しました。
こんなに面白いネタを、とことん掘り下げなかったのはもったいない!! という、愛ゆえのディスなのです。そしてこのリーマンの着想をもとに和音の変形操作を体系化しようとしているのがネオ・リーマン理論というわけです。
この「和音自体の記号化から、和音変形操作の記号化へ」というパラダイム・シフトはネオ・リーマン理論の思想の中核であり、またそれがおそらくは彼らが「ネオ」の名を冠する所以でしょう。
これは「接続系理論」の時に、並べられたコードそのものではなくコードとコードの間の変化を観察した話に似ていますね。分析の目線を変えることで、それまでとは違った発見が得られる。ネオ・リーマン理論も我々に新たな洞察力を与えてくれるはずです。
基本の変形操作3種
ネオ・リーマン理論における代表的な変形操作は、上譜で示したC⇄Cm,C⇄Em,C⇄Amに相当する変形です。
同主調関係にある和音間を切り替えるParallel、長3度関係にある和音間を切り替えるLeadingtone-exchange、そして平行調関係にある和音間を切り替えるRelativeの3つに関して、リーマンが機能名として使った名前をそのまま転用しました。これらはPAR, LT, RELと略されることもありますが、より一般的なのは簡潔にイニシャル一文字でP, L, Rと略するスタイルです。この3操作は、ネオ・リーマン理論系の多くの研究において基本操作として定義されています。
声部連結の倹約
ご覧のとおりPとLはたった半音動くだけ、Rも1音が全音動くだけと、声部の動きがかなりスムーズです。例えばCとEmは五度圏の理論で言えばE→A→D→G→Cという4回の5度連鎖ではじめて繋がる遠き存在ですが、そうではなくたった半音差で辿り着ける身近な存在であると捉え直すこと、和音進行に関して従来と異なる価値観を取り入れることに、ネオ・リーマン理論のひとつの意義があります。
このように和音どうしの繋がりを考える際のモノサシとしてルートの移動量よりも声部連結の移動量を重視する考え方は声部連結の倹約Voice-Leading Parsimonyなどと称され2、ネオ・リーマン理論を論じるうえでの重要なキーワードのひとつとなってきます。
リーマンが描く鏡面の世界
PLR操作の注意点として、各操作はコードがメジャーかマイナーかによってその内容が逆転します。R操作はメジャーコードにとって5thを全音上げることですが、マイナーコードにとってはRはその逆向きの操作を意味するので、これはRtを全音下げる操作となる。したがって、「3つの基本操作」とは言いつつも実質的には6パターンの変形が存在することになります。
そもそもなぜメジャーとマイナーとで処理が異なるという複雑な方法論になったのでしょうか? これは前回少し触れた「和声二元論」の思想が絡んできます。リーマンはマイナーコードをメジャーコードの完全なる上下反転と捉え、マイナーコードの根音は5thであるとまで言ったのでしたね。全ての法則が逆に働くので、P, L, Rの操作もメジャーとマイナーで上下すっかり逆さまにすることが、リーマンにとっては筋の通ったやり方だったのです。
むろんネオ・リーマン理論の論者たちは基本的に「5th根音説」は破棄していますが、この和声二元論が出自にあるがゆえ、メジャー/マイナーで操作が逆転するというユニークなシステムになっているわけです。結果として、PLR操作はいずれもコードの長短転換を伴い、また2回繰り返すと元の和音に戻るという特徴を持つことになります。ここには何か、「マイナスを2回かけるとプラスに戻る」みたいな、数学的な雰囲気も感じますよね。
PLR操作とルート変化
さて、「C-Emを3度上行ではなく半音ずらしと捉える」とは言っても、実際問題これらの操作によってルートの位置が何度移動するかは気になるところですね。改めて、転回形になっているところを基本形に直して、各操作でルートがどう変化するかを確認すると以下のようになります。
こうして見ると、長短3度の接続だけが基本操作に採用されていて、しかも上下行に関しても片方が欠けている(例:メジャーコードの短3度上行は基本操作にない)という、端的に言ってかなり変な世界観の理論であることがよく分かります。
それもそのはず、リーマンはまずT和音と5度上下の関係にある和音をD・Sとし、それ以外の和音をさあどうするという段階で出てきたのがこの平行和音であり導音転換であるわけで、5度進行がここにいないのは必然の帰結です。
またリーマンはキー内のコードを記号化することから始めたため、ダイアトニックコード内で起きることのない「メジャーコードの短3度上行」に対する記号も、存在していないわけです。この辺りの体系のいびつさに異を唱えたネオ・リーマン論者ももちろんいますが、これについては後述することにします。
5度、2度は?
このPLR操作だけをコード進行の“元素”として考えた場合、5度や2度の進行はこの操作を複数組み合わせた形でラベリングすることになります。
このように、CにL・Rの順序で変形をすればGとなり、逆にR・Lの順で変形をすればFとなる。したがってネオ・リーマン理論においては、MajからMajの完全5度上行はLR、完全5度下行はRLと表現されます。min→minやmin→Majとなるとまた手順が変わりますので、この辺りはなかなか煩雑さがあります。
2度上行の場合は、共通音がひとつもないですから、到達するまでに少なくとも3手かかることになります。
上譜のC-Dm, F-Emという例ではどちらも3手でしたが、コードクオリティなどの状況によってはさらにPの操作を挟んだりする必要が出てくるでしょう。
D操作
やっぱり3度の接続しか“元素”として持たないのはあまりにも装備が貧弱じゃないか? ということで、論者によっては5度下行をDOM、ないしDとして基本の変形に加えている者もいます3。その場合、例えばV-IVのような2度下行も「5度下行が2回分」としていくらかシンプルに記述することができます。
2度下行はDを2回行うのでD²と表記したり、あるいは5度“上行”ならD操作の逆をするのでD⁻¹と表記したりなど、数学に倣った表記を使う人もいます。
このD操作については、「使う文字は少なければ少ないほどいいから使わない」という論者と「あった方が便利だから使う」という論者とに分かれていて、流儀が統一されてはいません。
S操作・N操作
共通音を持つ和音の接続というのは他にもたくさん考えられますので、名前をつけようと思えばいくらでもつけられます。その中である程度の地位を獲得しているのが、SLIDE(S)4とNebenverwandt(N)5です。
“Nebenverwandt”は英語で言うと“Next-related”の意。確かに音の移動量を半音数で考えれば、半音2つの移動はR操作の全音1つ移動と等価ですから、名前をつけても悪くはないでしょう。N操作に関しては、I-ivの進行だけでなく古典派短調のケーデンスIII-viを一文字で記述できる点でも、採用すると便利そうです。
いずれにせよネオ・リーマン理論はとにかく3度の接続を特権化していて、他の接続に関しては二次的な扱いになります。しかしI-IV-V-Iやvi-ii-III-viといった基本のケーデンスと関わりがなく、従来のコード理論ではちょっと影の薄い存在である3度の接続をこんなに優先することに意義はあるのでしょうか?
2. 分析対象
ネオ・リーマン理論にはメインターゲットとする音楽ジャンルがあって、それが19世紀ロマン派のクラシック音楽です6。18世紀に古典派理論が大成し、20世紀には無調の理論が現れる、その狭間となる19世紀の音楽では、古典派の価値観から少しずつ逸脱しようとする挑戦的な作品が多数生み出されました。そうした作品の中では、局所的ではありますが意図的に古典派のお決まりのケーデンスに反旗をひるがえし、3度の接続を多用するようなシーンが実際に見られるのです。
こちらは1887年に作られた、ブラームスの『ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲』。270小節目の静かになったパートから、同主調の転換を何度も含む不思議な進行が見られますね。和音を分析すると、次のようになっています。
決して慣習的ではない進行ですが、規則的で何か美しいものを感じます。そして、3度の接続しか使われていない……。ここでネオ・リーマン理論の出番です。PLRの変形操作理論でこれを分析すると……
なんと、PLPLPLPという規則的な文字列が現れました! これはネオ・リーマン理論による分析がすごく功を奏した典型的な例です。従来の理論ではまあG♯m-E, Em-Cといったまとまりをセットと捉えてそれが長3度転調しながら繰り返されているという見方になりそうですが、TDSの機能感やディグリーで論じようとしてもちょっと判断が微妙な領域であり、そもそも5度進行の不在により調性がハッキリ確立されていないのに「転調の連続」と説明するのも何か楽曲の本質から遠ざかってしまう感じがします。
それよりも「PLPLPLP」と言われたほうが、スケールチェンジの繋ぎ目がルート移動のないパラレル転換で結ばれていることや、この進行全体を通じて半音差の移動しかないすごく“倹約家”な進行になっていることなどがズバッと伝わってきます。
こちらは1824年作、第4楽章が有名なベートーヴェンの“第九”こと『交響曲第9番』の第2楽章。V-Iが連続する典型的なカデンツの後、C-Am-F-Dm(I-vi-IV-ii)という3度下行の連続があって、3小節まるまる全員休符の時間が来ます。iiと来たら次はVへ行くのが古典派の“お約束”ですが、なんと次はDm-B♭-Gm-E♭と、さらに3度下行を続けるのです! そしてまた3小節の休みの後、さらにE♭からまた怒涛の3度下行が続いていきます。コードがAに至るまでの一連の進行をネオ・リーマン理論で分析すると…
なんと、RLRLRL RLRL RLRL RLRL。ただひたすらにRLの連続であることが分かります!
これも従来の理論で言えばまあI-vi-IV-iiの連続と見るところでしょうが、しかし規則的なメジャーとマイナーの繰り返しに対して片方をI-vi、もう片方をIV-iiとディグリーを振り分けるのはちょっとどこか恣意的な感じ、作品を調性音楽の型にはめ込んで解釈しようとしている感じがします。ベートーヴェンがここで構築しようとした規則的進行の美しさをどちらがより明快に浮き彫りにさせるかと言ったら、ネオ・リーマン理論の方に軍配が上がるのではないでしょうか。
III章終盤の記事では、「クロマティック・ミディアント」と呼ばれる非調性的な3度進行が映画音楽で活用されているという話をしました。そういった音楽もやはりネオ・リーマン理論が得意とする範疇になります。
またロック音楽でもC-E♭やC-A♭のような従来的な調性に収まらない3度の進行は何かと見られるので、中にはレディオヘッドやオジー・オズボーンなどのロックソングをネオ・リーマン理論で分析した論文なんかも存在しています。
ですから3度進行に特化した理論というのは、メイン・ウェポンにするには確かに限定的すぎるかもしれないけれど、しかし一部の音楽の特に一部の場面に対しては最適な分析ツールとなるのです。これは、エルネ・レンドヴァイの中心軸システムがトライトーン関係のアイデアを補完してくれるのに似ています。
このPLR変形操作がネオ・リーマン理論の代表的な内容となりますが、他にも面白い研究がいくつか含まれるので、それも紹介していきます。