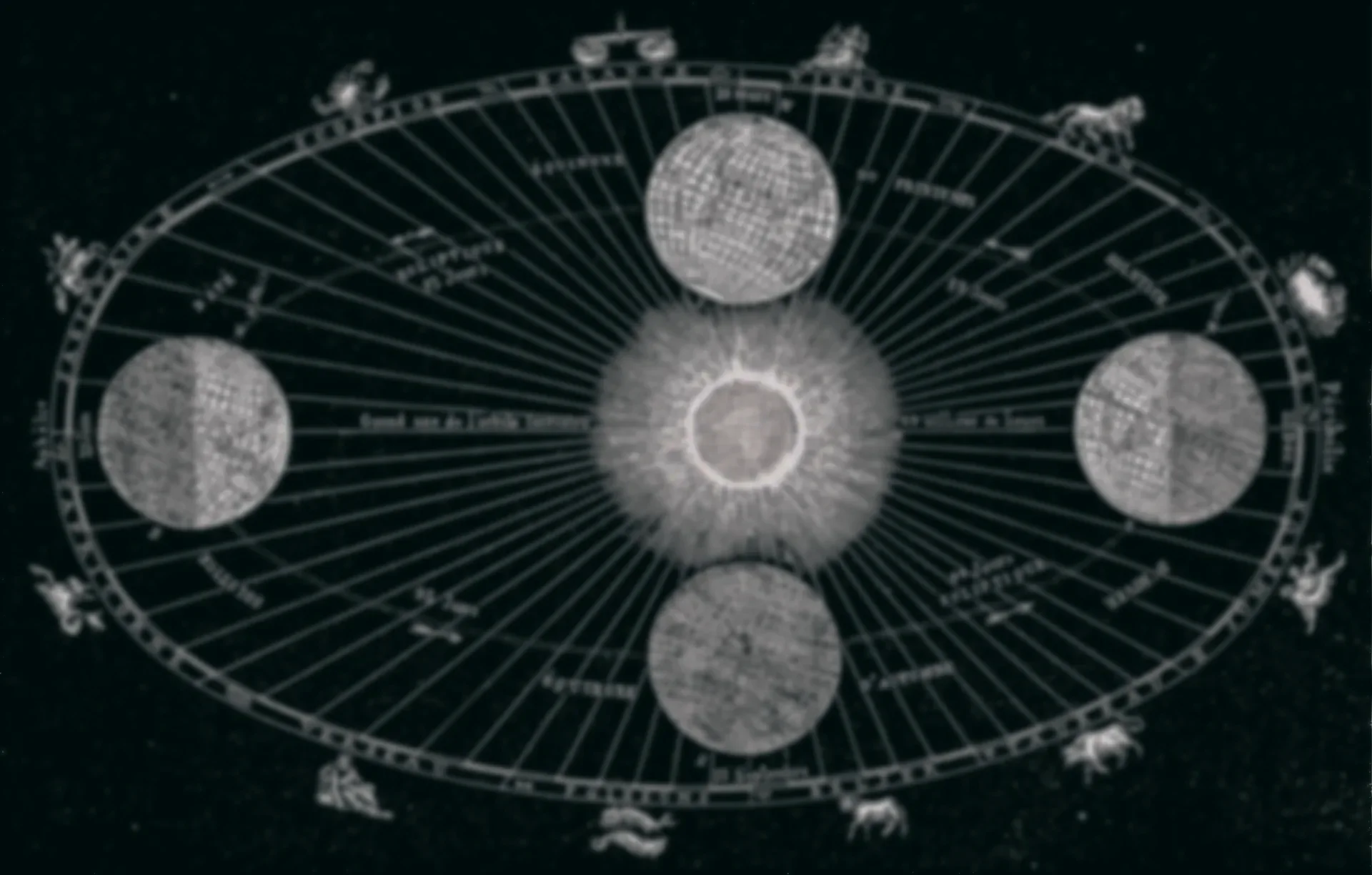目次
4. 中心音と音楽的終止
「音の組織関係」や「偏り」「傾向」なんて堅苦しい言葉で説明されて、ちょっと難しく感じたかもしれません。でも本当は、調性というのはもっと直感的で簡単ものです。前ページで無調性音楽を聴いて、普段ヒットチャートで流れてくるポピュラー音楽とは毛色が違っている、ミステリアスで掴みどころがないと感じたはずです。これは特別な音楽経験のない一般的なリスナーでも同じ感想を抱くでしょう。これってつまり、私たちは考えなくても調性音楽と無調性音楽の聴き分けができているということですよね。知識として調性のことを知ってはいなくとも、そのことを意識してはいなくとも、調性を感じてはいるのです。
これは決して不思議なことではありません。音楽経験のない人でも曲の明るい/暗いといったイメージを感じ取ることはできるし、中東風の音階を聴いて中東っぽいと感じることだってできる。私たちはこの世に生まれてたくさんの音楽と触れあう中で、実はけっこう音楽を記憶したり認識したり区別したりする力を養っているわけなのです1。
そしてソングライターにとっては、明るい/暗いといった雰囲気を使いこなすことが大事であるのと同じように、この中心音が生み出す音楽のストーリーを構築する技術は極めて重要なものとなります。実践的なフレーズメイクと中心音の関係性を見ていきましょう。
中心音と音楽表現
先ほど中心音を「終着点として機能する音」と説明しました。もう少し詳しく言うと、フレーズの終わりに中心音を用いることで、そのフレーズが“終わった”、“落ち着いた”、“着地した”という感じを最も明快に提示することができます。これはメロディライン、ベースライン、和音の組み立て、どれにおいても言えることで、曲の展開作りにおける最も基本的なヒントです。
中心に着地する表現
- ありがとう A
- ありがとう B
こちらはシンプルな感謝ソングですが、曲の終わり方を2種類用意してみました。Aは最後にメロディや楽器隊が中心音へと進んで終わる形。対するBは最後に中心から逸れていって曲が終わります。
ふたつを聴き比べると、最後にしっかりドッシリと完全に“終わった”感じが演出できているのはAの方です。メロディもベースも中心へと帰ってくることで、音楽に落ち着きが生まれ、「展開し終わって収束した」という印象を提示しています。Bの方はちょっと脈略のない方向へ進んでいて、ハッキリ言って良いメロディじゃありません。今回のようなストレートな感謝ロックソングであれば、ベタに中心音でビシッと終わるAの方が曲のメッセージがよく伝わるでしょう。
中心に着地しない表現
もうひとつ別のパターンも見てみます。
- まぼろし A
- まぼろし B
今度はせつないチルい系の楽曲で、また終わり方を2種類作りました。先ほどと同じく、Aは最後みんなが中心に着地して終わるパターン、Bは最後に中心から逸れていくパターンです。聴き比べていかがでしょうか?
この曲のテーマ性から考えると、Aの終わり方はしっかり着地を決めたばっかりに、かえって淡さや儚さのような情緒を損なってしまっています。対するBの方は、あえて落ち着かないまま終わることで「消えてしまった幻」という切ない雰囲気をバッチリ演出できています。この2つならBを選んだ方が、より多くの人の胸を打つ曲になるでしょう。ですから「パートのラストは中心音で終わるべき」というようなマナーがあるわけでは全然なくて、中心音に行くか否かでリスナーを落ち着かせるかどうかの駆け引きができるというイメージです。
この辺りのより詳しい内容はこれからメロディ編・コード編でドンドン解説することになっていて、今はひとまず具体的な説明も楽譜もなしに聴き比べをしてもらいました。もし現時点で「ありがとうAはストレートな感じがする」「まぼろしBは儚い感じがする」というのが聴いた直感でなんとなく分かるようであれば、それは素晴らしいことです。既にポピュラー音楽の定石が音感として身についているということですからね。
一方この違いが耳ではまだよく分からないという場合は、さらに理論学習や楽曲分析を重ねて知識を増やしつつ、作曲の実践経験も積みながら総合的に音感を鍛えていくことになります。感覚で分からないところを頭脳でカバーできることこそが理論の良さですから、ピンと来なくても前向きに読み進めてもらえればと思います。
実例を見る
実際のヒット曲のメロディにも、この中心音に着地するか逸らすかの選択を巧みに使いこなしている場面をたくさん見つけることができます。
HoneyWorks – 可愛くてごめん
『可愛くてごめん』のサビは、中心音のはたらきが非常に分かりやすい構成になっています。「ごめん」で終わるフレーズが4回あってひとまとまり、これが2周あって最後に「ざまあ」で終わる構成ですが、ここで4回登場する「ごめん」のメロディの違いに着目します。
こちらはサビのメロディ(前半一周分)のメロディラインを線で表現したもの。この曲はレの音が中心音となっていて、メロディが中心に対してどんな距離、どんな音高をとっているかを可視化しました。
色を変えたところが「ごめん」の箇所に相当します。その「ん」のピッチを確認すると、1回目と3回目は上の中心音へ、4回目は下の中心音へ着地していて、2回目だけはそのどちらからも離れたかなり中間の位置についていることが分かります。
そして実際に聴いてみた感じとして、2回目の「生まれてきちゃってごめん」のメロディではまだまだ続きがある感じがして、対する4回目の「気になっちゃうよね? ごめん」では一区切りついたような、そういった印象の差があるはずです。この印象差が発生する理由として、メロディが中心音に着地しているか否か、これが要因として大きいわけです。
あまり違いが分からないという場合は先ほどのAB比較の要領で、試しに4回目と8回目の「ごめん」、そしてサビラストの「ざまあ」を全て中心から逸れる2回目の「ごめん」のメロディに変えて歌ってみてください。メロディの明快な着地が失われたことで、何かパートが終わりきれない不満足感が残るはずです。
Ado – 新時代
『新時代』も、メロディが中心音へ進む/進まないの選択の妙が分かりやすい一曲です。冒頭で「変えてしまえば」と2度繰り返すところ、1回目は低い中心音へ着地しますが、2回目は高い中心音の方へ行くと見せかけて、そのほんの少し下を位置取ります。
かなり不安定な位置の音なので、ビタッとピッチを当てるのにはなかなかの歌唱力が要求される難しいメロディとなっています。もし中心に着地すればより安定した雰囲気でこの冒頭パートを終わらせることになるわけですが、曲の幕開けであるこの場面ではそのような選択をせず、宙ぶらりのままドラムが入り、ベースが入りと進んでいくことで、何かが始まるという緊張感をキープさせているのです。
そのまま曲が進んで1番サビ(1:28-)ではこのような“変化球”を仕込むような場面ではないので、2回ある「変えてしまえば」はどちらも中心音に着地します。ただし2回目の着地の後の動きがポイントで、「変えてしまえばーあぁぁ⤵︎」というふうに、また中心から離れる動きを見せます。
着地からすぐに再出発することで「サビまだ終わんないよ!もう一周行くよ~~!!」というメッセージを、メロディ自身が伝えているわけなんですね。
では2番サビ(2:57~)の方はどうか。ここは1回目こそ1番サビと同様に着地するものの、2回目は着地なしでまた中心から大きく離れた場所へと跳びます。しかも下に降りていった1サビとは逆で、上へと跳ぶのです。
中心から離脱することでサビ後半へと勢いを繋ぐという点は同じですが、こっちは上へと一気に跳び上がることで、より躍動感を強化してラスサビにふさわしい盛り上がりを演出しているのです。頭サビ、1番サビ、2番サビそれぞれで微妙に異なる旋律が絶妙に機能していることが分かります。
このように、同じ歌詞が乗るメロディの語尾だけを変えて音楽のストーリーに起伏を生み出すのはメロディメイクの基本的なテクニックです。こうしたメロディの表現法についてはメロディ編で詳しく扱っていくことになりますが、今回やった「中心音」という概念は、その土台となる大切な基礎知識でした。
簡単な統計
せっかく指標を得たので、簡単な分析を試みてみましょう。例えばApple Musicのプレイリスト「2010年代 邦楽 ベスト」の100曲を調べてみると、曲のラストフレーズの終わり方は次のように分布されました。
ちょっとサンプル数は少ないですが…やはりJ-Popだと、大衆性の観点から中心にしっかり着地するものがマジョリティになります。ポップスのヒットソング100曲のうち約8割が中心音で曲を終えているというただならぬ偏りがあった。「中心音」という概念を得たことで、J-Popが持つ傾向をひとつ客観的に見抜くことができました。こうやって目に見えない音楽を“視る”ためのツールが、音楽理論というわけです。
そんなわけでこの段階で、早速もう作曲をするのに最低限必要な根本はマスターしたも同然です!
- 全パートで同じ音階を使うとよい
- ピアノの白鍵7音を使って曲を作るのが一番初歩的
- その場合、ドが中心として働けば明るめ、ラなら暗めの曲調になる
- 中心に辿り着く動きとそこから離れる動きを駆使すれば音楽に明快なストーリー性が生まれる
「ひとつの音階を基本的に使う」「中心がある」ということがわかれば、初歩段階の作曲・編曲はそこそこ実践できます。
そして今後曲を聴く時にはぜひこの中心音の存在を意識してもらいたいです。中心音への着地が耳で認識できるようになると、それが音感を鍛える第一歩になりますからね。曲を作る際にも、中心の位置を意識しながら作曲することをお勧めします。
まとめ
- 楽曲の中で、音の偏りからある音が中心音として確立されます。
- 中心音とその他の音たちが作りだす楽曲内での組織的な関係性を、調性と呼びます。
- 多くの音楽は調性音楽に分類されますが、中には無調性の音楽も存在します。
- 中心音は音楽における終止・着地・安定を司っていて、それが楽曲の展開作りや表現に活用されています。