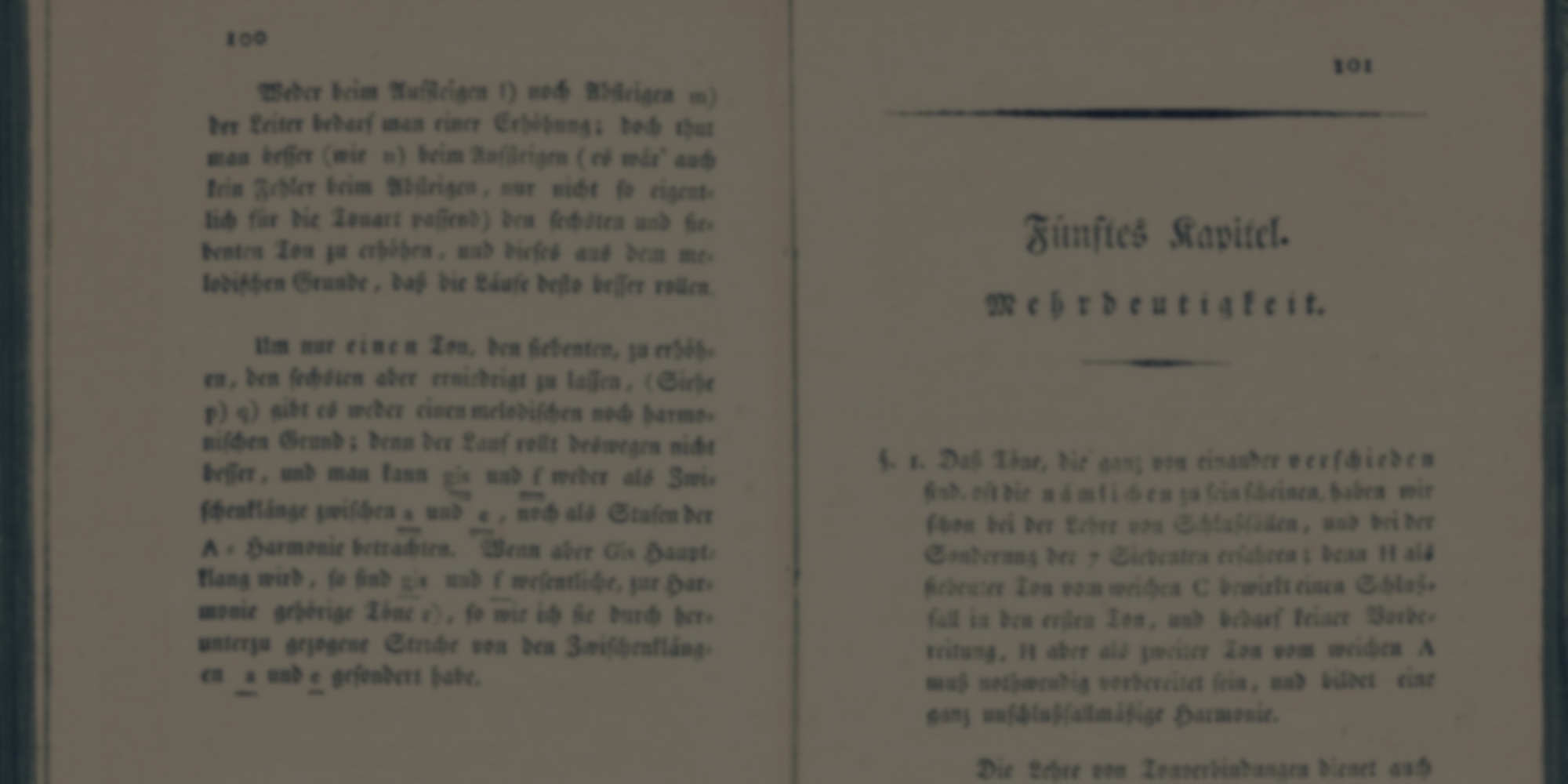目次
1. ポリセミー
このVIII章に至るまでに、「ある和音に対して複数の解釈が考えられる」「ある和音が複数の意味を持ちうる」といった状況は何度も登場しました。
そのような和音の意味の重複や不確定性に着目し、理論化に尽力した大家として知られるのが、ドイツの音楽理論家ゲオルク・ヨーゼフ・フォーグラー(1749 – 1814)です。フォーグラーは、このような”和音が内に秘める複数の意味”を、多義性Mehrdeutigkeitと呼んだのでしたね1。
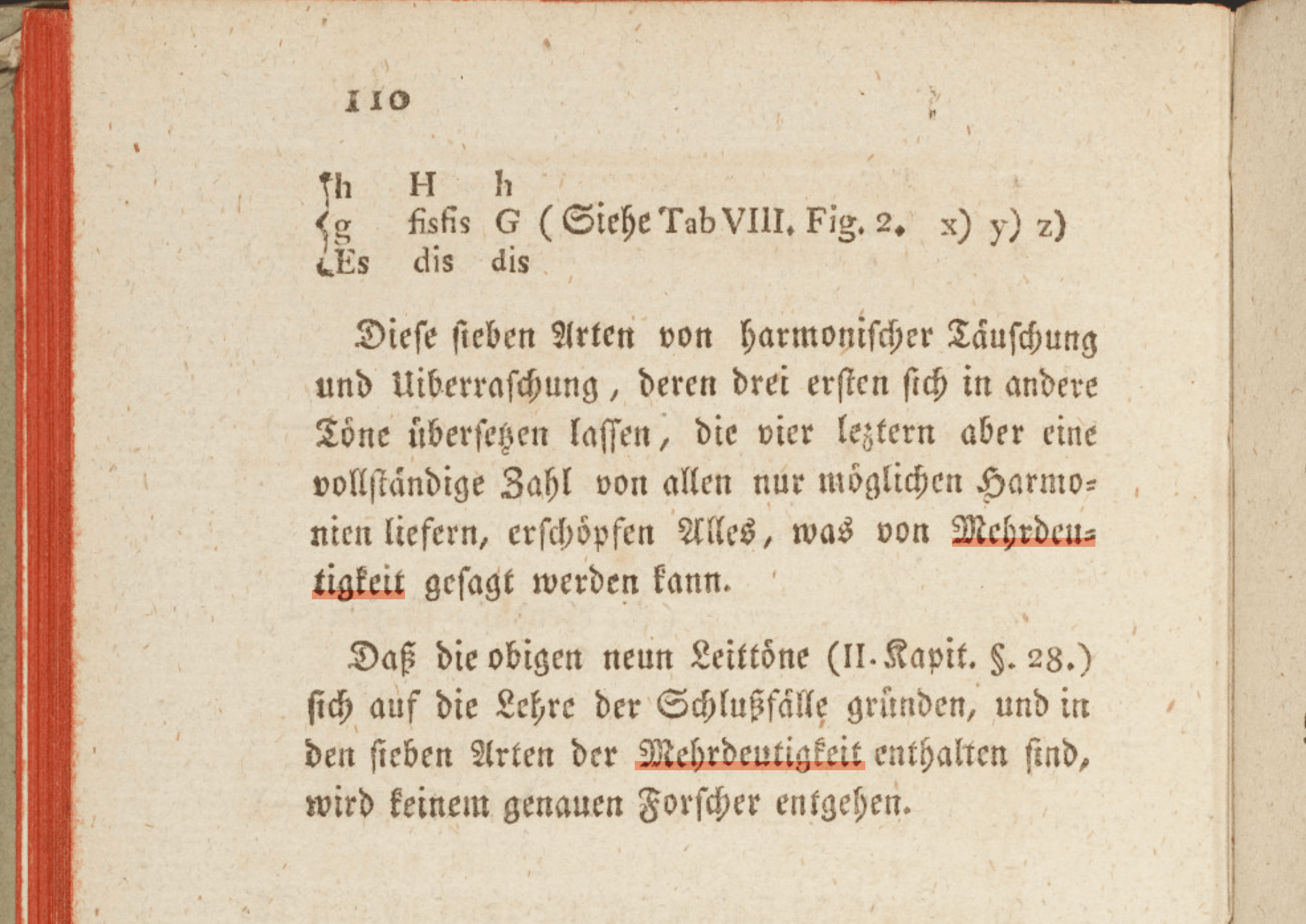
(1802) Georg Joseph Vogler “Handbuch zur Harmonielehre”
フォーグラーがローマ数字によるディグリー記法の礎を作った人物であることも、リーマンの歴史話の中で既に軽く触れました。ローマ数字記法が一般的と言えるレベルまで普及したのは、彼の死後ずっと後のことで、彼の志を継いだゴットフリート・ヴェーバーやジーモン・ゼヒターらによって少しずつ広まっていったのでした。
 1868 Principles of Harmony – F. A. GORE OUSELEY
1868 Principles of Harmony – F. A. GORE OUSELEYこれはフォーグラーの死後50年経った頃の理論書。I7を利用して下属調へドンドン転調していく説明だと思うのですが、2個めの和音では「♭5 6」と単に度数の堆積が表されているだけで、ディグリーがないせいで起きていることが分かりにくいですね。
フォーグラーはこの状況を「どげんかせんといかん」と立ち上がった黎明期の重要人物ということで、現代の私たちもその恩恵を大いに授かっています。
Mehrdeutigkeitを英訳する
この記事ではこの「Mehrdeutigkeit」について本格的に扱うわけですが、ちょっと長いし読みづらいということで、ここではダナ・グーリーという音楽博士が用いたポリセミーPolysemyという英訳を採用しようと思います2。
この語は日本語でいうところの「多義性」とほぼ同義です。また同様にして、「多義的」という言葉を横文字で表す場合には、ポリセミックPolysemicという語を一貫して使うこととします。
- 多義性 (Polysemy)
- ある和音が複数の意味を持ちうる状態にあるという性質。
- 「多義」の対義語は「単義」や「一義」など。英語ではモノセミー、モノセミック。
前回の記事では、「音響の論から認識の論へ、構造の論から意味の論へ」という投げかけで終わりました。ポリセミーの価値観を理解することで、またひとつ見える世界が変わります。
2. モノセミーからの解放
ポリセミー論に入っていく前に、日常の私たちがいかにモノセミー視点に偏りがちであるかを自覚し、まずそこから意識的に解放される必要があります。
演奏とモノセミー
例えば理論を「演奏」に活用する際、すなわち楽曲の骨がいくらか固定された状態でそこに演奏を乗せる際には、理論は音楽をモノセミックにするために用いられます。
背景スケールが分からなければアドリブ演奏ができないから、あいまいはよくない。CよりもCΔ7、CΔ7よりもC Ionianと、詳しく記述することで音楽を正しく認識できる、というモノセミーの価値観が根底にあります。
分析理論とモノセミー
あるいは楽曲を「分析」する際も、やはり音楽をモノセミックな状態に確定させることを目標としてこれを行っています。
異名同音の識別、根音省略も含めたルート音の判定…そういったものを通じて、作曲家が何を意図してその和音を用いたのかを解き明かしてやろうというモノセミーが、やはり求められます。どんな和音が出てきたって「これは○○である!」と言える人がスゴイ。そういうモノセミーの価値観が、根底にあるわけです。
演奏のときにも分析のときにも、「正体不明」というのは“招かれざる客”です。それを無くしていくために音楽理論は頑張ってきたのだと言っても過言ではありません。これを「何だっていいじゃん」で済ませてしまったら、それは思考停止、挑戦の放棄と捉えられます。
作曲とモノセミー
一方で、いざ自分が作曲する側に回ったらば、そんな話は全く関係なくなります。確かに自分が作っている音の意味は理解していた方がいいし、モノセミーになっている音楽はリスナーにとっても分かりやすいでしょう。しかしあえてモノセミックにしないという方法がオプションとして常に存在します。例えばコード識別にとって重要な3rdや7thを鳴らさないとか、綺麗な3度堆積構造にしないとか、そういう様々な方法が戦術のひとつとしてある。
もしここで「演奏」や「分析」のマインドに引っ張られてしまうと、当たり前のように「コードネームから」「スケールから」展開を考えてしまって、そういう特殊戦術は引き出しの奥の方へとしまいこまれてしまう危険があります。
音楽のポリセミーについて漠然と認識するのではなく、きちんと理論的に整備することで、どこまで演奏したらリスナーはどこまで意味を特定するのか、どうすれば複数の文脈を合流させることができるのかを掌握したうえでコントロールすることができるはず。そしてその能力を活用すれば、普段のモノセミックな発想では辿りつきづらいエキセントリックな表現をスムーズに引き出すことができるはず。
だからこれまでの通常モードであった「音の意味をしっかりと分析し、識別しよう」という“優等生”のスタンスをいったん忘れて、「どうすれば他人に簡単に識別されないような和音が作れるか」という、180°ひっくり返した視点で音楽理論を活用してみるというのが今これからやるポリセミー論なのです。
例えばシナリオの世界では、人物が死んだか生き延びたか不明だとか、夢なのか現実なのかがハッキリしないみたいなやり口も、ひとつの定石として当然のように含まれています。ときに解釈の余地を“あえて”残すことが受け手の想像力をかきたて、よりストーリーに深みを与えることを知っているからです。
彼らは感覚ではなく「セオリー」としてそれを持っています。解釈を単一に絞り込ませないための入念な伏線張り、精密な表現というのがあって、こうすると片方の解釈に偏っちゃうからここのラインで、というのを見極めて作品を作っている。じゃあ音楽でも同じことができるんじゃないか、ということです。
厳密なモノセミーのその先
ポリセミーを考えるにあたっては、これまで培ってきた「音楽を識別する能力」はムダになりません。それどころか、その識別能力がポリセミーを操るカギとなります。だって、前回やった「減4度」「増6度」の存在を理論的に把握していない人間は、たとえ感覚で減4度を減4度として使っていたとしても、それを長3度にすり替えようというアイデアにまではたどり着けないでしょう。識別能力が繊細であればあるほど、それだけ「すり替え」「重ね合わせ」のパターンを閃けるというわけです。