目次
今回紹介するのは、「リディアン・クロマティック・コンセプト(Lydian Chromatic Concept, LCC)」という理論。ジャズ作曲家であり音楽理論家であるジョージ・ラッセル氏が1953年に出版した書籍にて述べられている、ジャズを主要なターゲットとした特殊な理論です。
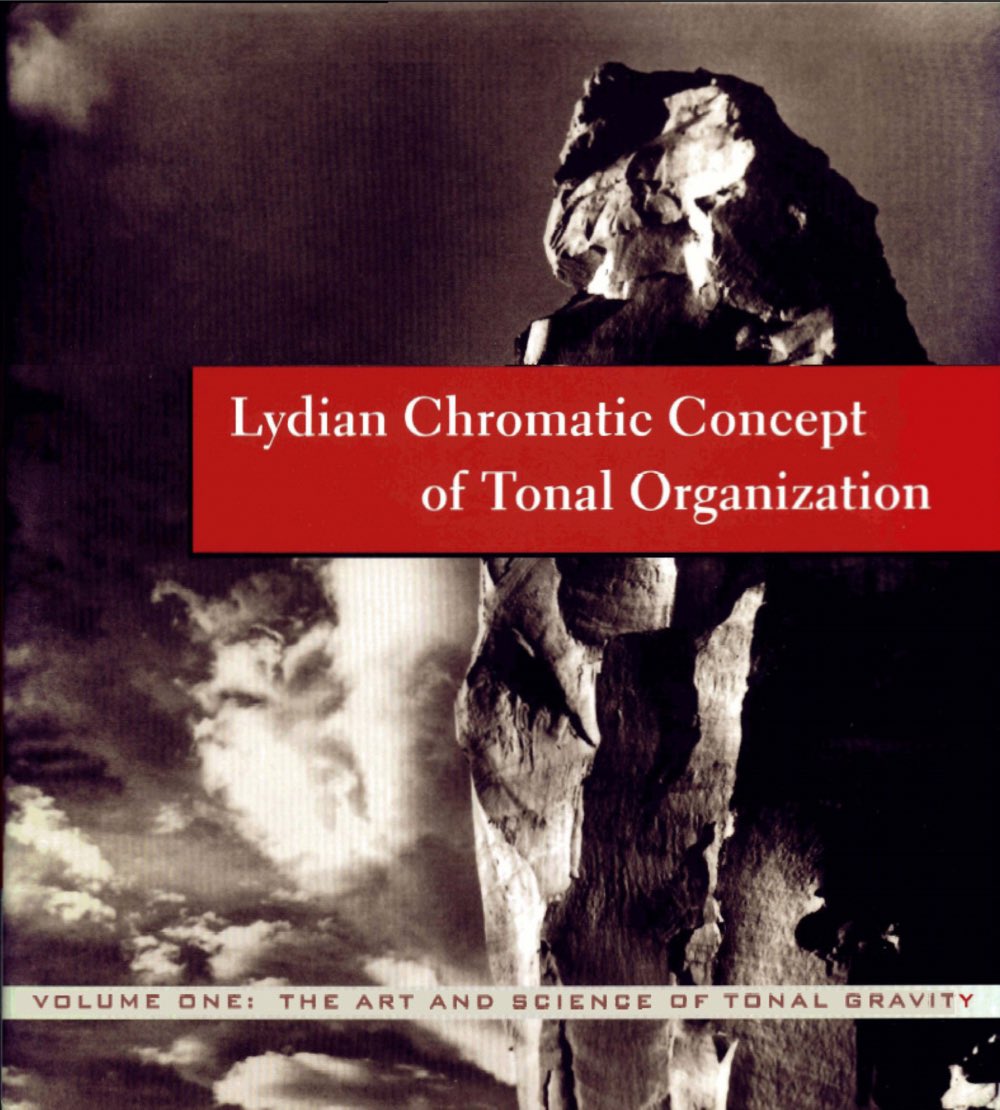
1. LCCとは
今回は前回の「中心軸システム」に引き続き、理論家が提唱した特殊理論の回です。「中心軸システム」があくまでもバルトークの楽曲分析のために用意された限定的な理論であったのと同様に、今回もまた、現行のポピュラー音楽にまるっと当てはまるようなタイプの理論とは異なります。そこで、少しこの理論にまつわる時代背景や著者の人物像を先に紹介しておきます。
当時のジャズの状況
1940年代にビバップが発展し、「コード進行に合わせて即興演奏をする」というスタイルについては、その10年でおよそ完成したような状況になりました。
そして1960年代にはモード・ジャズだったりフリー・ジャズといった新スタイルが登場する……
……というのがごく大まかなモダン・ジャズの流れなわけですが、そうするとLCCが発表された1953年はまさにその狭間に位置する、過渡期であったと言えます。そしてジャズドラマーとしての出自を持ち、作曲家・音楽理論家であったジョージ・ラッセルは、1940年代の段階でマイルス・デイヴィスとの対話の中でインスピレーションを受け、このLCCという理論を構想したといいます。
Russell’s path to his theoretical magnum opus was charged by an encounter in the first half of 1945 with Miles Davis, who answered Russell’s question about his musical goals by stating that he wanted “to learn [to play] all the changes (chords)” (Russell [1953] 2001, 10). Davis already possessed considerable harmonic knowledge at the time; he was performing in various New York jazz venues and had famously attended Juilliard the year before. His “all” in “all the changes” therefore points to harmonic knowledge that exceeds Western art music theory and bebop; it expresses a desire to relate any pitch to any harmony.
ラッセルが自身の代表作となる理論書へと歩み出すきっかけとなったのは、1945年前半のマイルス・デイヴィスとの出会いであった。ラッセルが彼に音楽的目標について尋ねた際、マイルスは「すべてのチェンジ(コード)を弾けるようになりたい」と答えたという(Russell [1953] 2001, p.10)。
当時のデイヴィスはすでにかなりの和声的知識を有しており、ニューヨークの様々なジャズ・ヴェニューで演奏していたほか、前年にはジュリアード音楽院にも在籍していた。したがってこの文脈における「すべて」という言葉には、西洋芸術音楽やビバップを超えたハーモニーの知識、つまりあらゆる音をあらゆる和音に繋げたいという欲望が込められていたと言えるだろう。Hannaford, Marc E. (2021) Fugitive Music Theory and George Russell’s Theory of Tonal Gravity (pp.53-54).
そうして彼が作ったLCCは、実際にマイルス・デイヴィスに影響を与えたとも言われます。またジョージ・ラッセル自身も作曲家としてこの理論を実践し、1985年にリリースした『The African Game』は、翌年の第28回グラミー賞のジャズ系2部門にノミネートもされています。
コードやスケールの理論の多くは実践が先にあって、それをまとめた結果としての理論があるという順序で出来上がっていますが、このLCCは従来の西洋音楽やビバップを超えるために意図的に編み出された、いわば人造の音楽理論です。したがってその毛色としては、シェーンベルクら20世紀の現代音楽家たちが行ったチャレンジによく似ていますね。実際に「Event V」のピアノなんかはずいぶん現代音楽然とした不思議な和声を紡ぎ出しています。いま慣習的になっている様式とは根本的に違う発想をベースにして理論を作ってみよう。そしたらきっと聴いたことのないような新しい音楽が生まれるはずだ——。
このような前提を踏まえたうえで、本論に進んでいきたいと思います。ただ先に断っておかねばならないのは、この記事ひとつで紹介できる内容はごくごく限られているということです。一般的なコードスケール理論の基礎を解説するのにも、なんだかんだで9回もかかりました。それよりもずっと複雑なコンセプトであるLCCの内容をコンパクトにまとめるなんて、できません。これはあくまでもLCCに興味を持つきっかけとして、おおよその概要を知ってもらう目的としての記事だということを了承ください。
2. リディアンスケールと統一性
さて、それでは慣習と根本的に違う発想とは何か?それはずばり、メジャースケールよりもリディアンスケールの方がより根源的であるというアイデアです。
このリディアンスケールが、メジャースケールよりも音楽の統一性(Unity)を体現している存在であると捉え直すところからLCCはスタートします。これは当然メジャースケールを基本とする西洋音楽の慣習と実情に反していますが、しかしこのようにあえて慣習から離脱するからこそ、従来の音楽とは異なる新しいハーモニーを生み出すための理論が構築していけるわけです。実際にジャズでは、アヴォイドノートがないことから、アイオニアンよりもリディアン、エオリアンよりもドリアンが選ばれる場面というのがある。ジャズ系理論の出発点として、まんざら無くもないアイデアです。
統一性(Unity)について
メジャースケールにおける音楽というのは、特性音であるファの音がもつ傾性によって形作られるといっても過言ではない。そのことをLCCでは以下のように述べています。
The major scale represents the horizontal, musical active force forever in the state of resolving to its I major or VI minor TONIC STATION goal (cadence center).
メジャースケールは水平的で音楽的である「能動的な力」を象徴し、常にIかVIの「トニック・ステーション」という目標(ケーデンスの中心)へと解決に向かう状態にある。
そして、メジャースケールのトニックへと向かう欲求を「ゴールへの圧力(Goal Pressure)」と表現しています。
メジャースケールが「水平的」で「能動的」にトニックへ向かっていくのに対し、リディアンスケールは「垂直的な重力」を持ち、「受動的」な力としてそこに在り、「自己組織された統一性(self-organized Unity)」を持つと説明します。
この「垂直」と「水平」の対比はLCC全体に横たわっていて、簡単に言えば、VI章コードスケール理論で扱ったような「1コードに対し1モード」という価値観が「垂直」で、大して「ii-V-Iは結局Iのメジャースケールで全部弾ける」というコード横断的な見方が「水平」ということになります。
LCCではまず垂直的な理論組みから始まりますが、話が進むにつれて水平的な視点が加わってきて、そうすることによってアドリブの自由度がさらに大きく増し、新しいサウンドを生み出していける。全体としてはそういった流れになっています。
論拠について
とはいえメジャースケールの圧倒的独走状態である現状でいきなり「リディアンの方がふさわしい」といっても、誰も信じてくれません。そこで書籍の序盤は、なぜリディアンがUnityを体現しているかの説明がしばらくなされます。例えば説明のひとつとして挙げられているのが、「完全5度の結びつき」です。Cに対して最もよく結びつくのは、Cの完全5度上であるG。これは間違いないです。そしてこのV-Iの関係を連続させていくと、Fより先にF♯が現れる。
Cというリーダーへ向かって直列的に繋がっている音はF♯なのである。だから、Fの代わりにF♯を使ったリディアンスケールは、Cに向かって綺麗に繋がっていく、最も統一されたスケールなのであるとLCCでは考えます。
序盤では他にも様々な話を持ち出してリディアンスケールの統一性について説明しているのですが、実のところそれはこの理論にとって本質的に重要ではないので、割愛します。この辺りについては、記事の最後の方でまた触れることとします。
3. リディアン・クロマティック・スケール
次にLCCでは、先ほどの「完全5度で数珠つなぎ」を発展させて、12音を網羅したリディアン・クロマティック・スケールLydian Chromatic Scaleを完成させます。
I,V,II,VI,III・・・と並ぶこの序列をLCCではトーナル・オーダーTonal Orderと呼びます。この序列がいわばIとの結びつきの強さを表すわけです。システマティックに考えればこの序列の8番目にF♯の音が登場するべきですが、これはルートと短2度の関係、流石にこれがIと結びついているというのは無理があるということで、例外的に序列の最後にまわっています。
リディアン・クロマティック・スケールが単なるクロマティック・スケールとは違うのは、この「序列」の情報を内在している点です。この序列をもとに、サウンドがリディアンスケールの重力を支える方向に働くか、重力から外れる方向に働くかを統一的に論じていくのです。
トーナル・オーダーの序列が高いものは「イン・ゴーイングIn Going」、低いものは「アウト・ゴーイングOut Going」であると説明されます。抽象的な言葉ですが、イン・ゴーイングはサウンドに「落ち着き・まとまり」を与えるもの、アウト・ゴーイングはサウンドに「外した感じ」を与えるものといったところです。おそらくジャズでいうインサイド・アウトサイドに近い意味合いだと捉えて差し支えないでしょう。
4. プリンシパル・スケール
そして先ほどの序列に基づいて、リディアン・クロマティック・スケールから音を選んで、計11個の音階を作ります。そのうち特に重要となるスケールが、7つのプリンシパル・スケールPrincipal Scalesです。日本語で言うなら、「七つの主要音階」といったところでしょう。
この記事の続きを読むには、ログインが必要です。サイドバーのログインフォームからログインしてください。メンバー登録は無料で可能です。
先ほどの序列(トーナル・オーダー)が頭に入っていると、この7つのスケールは分かりやすいです。トーナル・オーダーの上位7音だけで作られた最も基本的な音階が、もちろん「リディアン」。そしてオーダー8,9,10位の音をそれぞれひとつずつ埋め込んで作ったスケールが、「リディアン・オーグメンテッド」、「リディアン・ディミニッシュト」、「リディアン・フラットセブンス」なわけです。
「リディアン・オーグメンテッド」「リディアン・フラットセブンス」については、メロディックマイナーを親にした時の第IIIモード、第IVモードですが、LCCではこのように、「リディアン・クロマティック・スケール」から全てが生まれると考えます。
そしてオーダー8と10を両方埋め込んでVIを無くしたのが「オグジュアリー・オーグメンテッド」。オーダー8,9,11を入れたのが「オグジュアリー・ディミニッシュト」で、唯一P4thのインターバルを持つスケール。最後に、オーダー9,10,12を入れたのが「オグジュアリー・ディミニッシュト・ブルース」になります。
最後の3つについては、インターバル編成になんだか見覚えがありませんか? 実はこの3つ、コードスケール理論では別の名前で呼ばれている既知のスケールですね。
| LCCでの呼び名 | 一般的な呼び名 |
|---|---|
| Aux. Augmented | Wholetone |
| Aux. Diminished | Diminished |
| Aux. Diminished Blues | Dominant Diminished |
CSTでは、この3つはメジャー、メロディックマイナー、ハーモニックマイナーのいずれからも生まれないため、後ろの方の回で追加紹介した者たちです。それらが「七つの主要音階」として名を連ねている。
明らかに普通でない、どちらかと言うと飛び道具的存在として認識されているスケールたちを、あえて基本に据えてシステムを作る。そうすることでLCCはより発展的な創造性を生み出そうとしているわけです。
4つの水平的スケール
LCCではさらに、補助的にもう4つのスケールを加えて、合計11のスケールを基盤にして進めていきます。残り4つは以下のとおり。
| LCCでの呼び名 | 一般名 | インターバル編成 |
|---|---|---|
| Major | Major | I II III IV V VI VII |
| Major Flat 7th | Mixolydian | I II III IV V VI ♭VII |
| Major Augmented 5th | Ionian ♯5 | I II III IV +V VI VII |
| African-American Blues | Blue Note | I (II) ♭III III IV +IV V VI ♭VII (VII) |
これらはP4thのインターバルを持つことから、「水平的」であると評されます(Auxiliary Diminishedはどうなんだという気もしますが・・・)。先ほどの「7つの主要音階」と違い、こちらは例の「ゴールへの圧力」「水平的で能動的な力」を持つスケールとされ、これらについては後の方の章で論じられることになります。
LCCではこれら11個(特に7つの主要音階)を使って音楽を構成していくことになります。
5. 対応スケールを見つける
そうすると次はコードスケール理論と同様、コード対して対応していく音階をあてていくという話になります。しかし、音階を当てはめるといっても、その方法論はこれまでに2種類ありました。
一般音楽理論のメソッド
ひとつは、キーの中心を基準にしてモードをあてる方法です。
ようは一般的な音楽理論の世界で用いられる方式であり、この方式においては「モード」という概念は存在せず、スケールの上にコードが分離したような状態で同居しています。コードが何であろうと、それとは別にスケールのセンターが存在する。上の例でいえば、コードが変わってもキー・トニックはずっとCです。
この方式はスリムで便利ですが、キーに依存したメソッドのため頻繁な転調に対応できず、モード・チェンジの発想がしづらいという欠点がありました。
CSTのメソッド
そこでコードスケール理論では、コードのルートを基準にしてモードをあてる方法を提案しましたね。
CSTではモードの中心を「モーダル・トニック」と呼ぶことで、「キー・トニック」から独立して音階を捉えることにしました。習得が大変なぶん、キー非依存となってコードごとのテンション・アヴォイド情報までもが内臓され、モードの交換による発想を広げていきやすくなりました。
しかしLCCが行うモードとコードの対応法は、このどちらとも異なります。
リディアン・トニック
LCCは、何についてもリディアン・スケールを中心に物事が動いています。だからLCCの考え方はシンプル。どのコードに対しても、リディアンスケール(もしくはそれに次ぐ6つの主要音階)を親にしてあてていくのです。Cメジャーキーを例にとると…
たとえばFΔにはもちろんFリディアンをあてるし、CΔに対してもCリディアンをあてます。
CリディアンのばあいF音にシャープがつくわけですが、LCCにとってこれは最も統一性のある状態であり、平常状態です。こうすることで、「不安定なアヴォイドのF音を解決せねば」というプレッシャーから解放されると考えます。
じゃあG7に対してどうするかというと、これにはFリディアンスケールをあてるのです。確かにFリディアンなら全部“白鍵”の音ですから、G7に対応はできます。
「ルートがGだからGリディアン」でもなければ、「キーがCだからCリディアン」でもないというのがポイント。この選び方は、一般的な音楽理論ともコードスケール理論とも違いますよね。
| 理論系 | 適用するスケール(モード) | スケール(モード)の中心 |
|---|---|---|
| 一般理論 | Cメジャースケール | C(=キーに依存) |
| CST | Gミクソリディアン | G(=コードに依存) |
| LCC | Fリディアンスケール | F(=どちらでもない) |
LCCの方法論は、キーに依存していないという意味ではCSTに近いが、コードとは別にペアレント・スケールの中心があるという点では一般理論に近い。ちょうど2つの“合いの子”のような独特の発想をしているのです。
LCCでは、この「モーダル・トニック」とも「キー・トニック」とも異なる「ペアレントスケールの中心」のことを「リディアン・トニックLydian Tonic」と呼ぶことにしました。
メジャーセブンス以外のコードでは、モーダルトニックとリディアントニックは原則ずれます。クオリティごとの「ずれ」を覚えておかなければいけないのが、LCCを難しく感じさせる大きなポイントなのです。この「モーダルトニックとリディアントニックの間のインターバル」のことを、リディアン・トニック・インターバルLydian Tonic Intervalと呼びます。たとえばG7におけるL.T.I.は、「短7度」ないし「長2度」です。
2-5-1-6にスケールをあてる
ココは結構な躓きどころなので、もう少し例を付け加えますね。たとえばジャズでよくあるii-V-I-viの進行のばあい、次のようになります。
A–7に対しても、強傾性のF音を避ける目的でC Lydianがあてがわれる。やはりジャズという文脈内では、ファ♯は何ら問題なくKey Cの調性内に存在できていますね。
この「スケールの適用」を身につけた段階で、まずこうやって簡単な演奏が出来るようになるので、ようやくLCCの最初の一歩を踏み出したというところです。
しかしこの段階では、まだ何のためにこんなことをしているのか分かりませんね。序盤で紹介した「7つの主要音階」も全く活かされていない。この先に進んでようやくLCCの意義が見えてきます。




