教会旋法やその他スケールの使い方について(特に前者)
- このトピックには2件の返信、3人の参加者があり、最後に
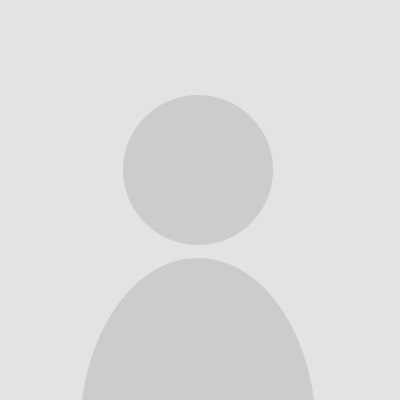 taro yamadaにより4ヶ月、 1週前に更新されました。
taro yamadaにより4ヶ月、 1週前に更新されました。
-
投稿者投稿
-
2025.7.21 18:04
皆さん今晩は、いつもお世話になっております。
今回の質問なのですが、もしかしたら凄く基礎的な事で、
皆さんに質問するのも恥ずかしいのかもしれませんが・・・
いわゆる教会旋法てどう使うのですか?
この質問の仕方だと漠然としてるかもしれないので、具体的に書くと・・・
例えば、ミクソリディアンが使われているとされている恐らくDメジャーキーの曲で、
楽譜の最初に調号が#2個付いてて、D-|-D-|-C-G-|-Aというような4小節の進行で、
1小節目のDの時にナチュラルのドの音が鳴っている場合、これはDミクソリディアンが
使われている・・と思うのですが、3小節目のCの時にもナチュラルのドが鳴っていまして
その場合はどう解釈したら良いのでしょうか?Cミクソリディアンでしょうか?
というかこちらが本題なのですが、大前提としてこういう教会旋法を始めとしたスケールって
曲のキーに対して使う、例えばDメジャーキーの曲ならDミクソリディアンで、
それを転調でもしない限りは曲を通して使うのか、
(Cメジャーキーの曲でCメジャースケールを曲を通して使うみたいに)
それともコード1つ1つに対して使う、例えば上記の曲の進行なら
コードがDの時はDミクソリディアン、Cの時はCミクソリディアン~
みたいな使い方なのか、どちらなのでしょうか?
なんとなく後者のような気もするのですが・・・
かなり悩んでいて独学だとどうにも解決しないので、どなたか、ご教授お願いします。
2025.7.27 21:17初めまして。私も未熟ですので、疑いを持ちながら読んでいただきたいのですが、その前提で私なりの解釈をお伝えさせてください。
まず、大雑把に「コード進行によって構成された曲(コーダルな曲=普通の曲)」と「旋法を重視した曲(モーダルな曲=モードジャズや民族音楽(風)など)」の2種類があると私は理解しています。
SoundQuestでの「教会旋法」は後者の文脈で紹介されていると思います。モーダルな音楽では、コードチェンジは登場しますが、ドミナントモーションのような強い進行(接続)は基本的にはなく、特性音を強調しつつ、メロディでトニックを認識させるような手法が取られます。
この場合、曲を通じて一つの旋法(モード)というのが一般的だと思います。4小節ごとに旋法が変わるというようなこともありますが、いずれにせよある程度の長さで持続的に特定の旋法が用いられます。
次に、コーダルな音楽の話ですが、ここでも「ミクソリディアン」のような旋法名は使われることがあります。これが混乱のものになっているのではないかと思います。
コーダルな音楽の場合、Dメジャーキーであれば基本的にはDイオニアンです。このときに「A7(ドミナント)ではAミクソリディアンが使われる」などと説明される場合があります。構成音は同じなので、別にモードが変わるわけではありません。そのコード上で利用可能な音を示すためにモードの名前を使っているだけで、モーダルな音楽での旋法名とはニュアンスが違います。
ジャズ的な文脈であれば、キーDのA7でAミクソリディアン以外のスケールを使うかもしれません。そのときに例えばオルタードスケールやHMP5や…といったスケール名が登場しますが、これもモードというよりA7というコードをどう解釈するか(どういうテンションを想定するか)に結びついています。
—
一応、コーダルとモーダルの間くらいの音楽を想定することもできまして、代表的なものがブルースだと思います。
Dブルースでは全体を通してDイオニアンやDミクソリディアンが使われるわけではなく、D7の時はDミクソリディアン(やDドリアンやDマイナーペンタや…)、A7のときはAミクソリディアン(同)、G7のときは…とスケールが移り変わると思います。(これも演者の解釈次第で、Dマイナーペンタ一発で弾く人もいると思います)
他にも、モードジャズの派生で、頻繁に(1小節ごととかで)モードが移り変わるようなものもあります。同じモードが並行移動するようなものが多いでしょうか。
—
遅くなりましたが、結論としては、この曲が一般的なモーダルな曲として想定できるのであればCコードの位置でもDミクソリディアンを使用するのが普通かと思います。この場合、最後のAは補助コードと解釈することになります。(Dミクソリディアンを想定するとダイアトニックコードはA-になるはずなので)
補助コードについて→ https://soundquest.jp/quest/melody/melody-mv3/dorian-scale/2/一方で、ブルースや、モードが激しく移り変わるタイプの曲であるなら、CコードでCミクソリディアン、GコードでGミクソリディアン、というふうに使用する可能性も否定できません。
2025.10.3 16:07はじめまして。
教会旋法の活用は難しいテーマですよね。
私なりに順に考えてみたいと思います。
①(in D mixo)D -> C -> G -> Aという進行におけるスケールの解釈について
まず、D mixolydianのスケールを確認します。
D mixolydianのスケールは[D, E, F#, G, A, B, C]となります。 (以降 D mixoと略してます)次に、Cメジャーコードの上でナチュラルのドがなっているとのことで、この場合の解釈について考えてみます。
ナチュラルのドについては絶対音程として素直にCと解釈するか、相対音程としてのドであれば、スケールから見た場合Dであり、Cメジャーコードから見た場合Cということになります。ここでは絶対音程のCとして話を進めてみます。Cメジャーコード上でCがなっているということは、D mixoから見てもCメジャーから見ても特別音の変化があるわけではないと考えられます。つまりCメジャーコード上でも引き続きスケール = D mixoとして旋律が構築されていると考えて差し支えないと思います。
つまり、メロディのスケールとしてはD mixoで一貫しているといってよさそうです。
次に、Cメジャーコード上でどのような音が鳴らせるかという観点から考えてみます。
かりにCメジャーコード上でC mixoと仮定した場合、構成音は[C, D, E, F, G, A, Bb]となりますので、mixoの特性音である7音目、Bbがどこかで案内されているはずです。(例えばコードがC7だったり、メロでBbがなっている等)
しかし特別そういった音はなっていないようですので、その場合は引き続きD mixoのスケール上の音が使えると考えるのが自然です。
D mixoをCメジャーコードから見た場合[C, D, E, F#, G, A, B]となります。これはC lydianスケールの構成音と同じであり、Cメジャーコード上でならせるスケールはC lydianということになります。まとめますと、
・メロディのスケールとしてはD mixoで一貫していると考えてよさそうです
・Cメジャーコード上で利用できるスケールはC lydianといえるでしょう。これは音楽を旋律的な横の流れで見るか、コード上でどの音を使ってよいのかという縦の視点で見るかによって違うスケールに見えるということです。
なかなかややこしいですよね。②教会旋法の実践について
〇旋法は転調しない限り一曲を通じて使い続けるものなのか
曲中で旋法がかわることはありますので、使い続けなければいけないというものではないと思います。
例えばぱぴぷぺ☆POLICE!という曲ですが、この曲は冒頭D aeolian、Dマイナースケールから始まり、AメロではD mixolydian的な音使いをしています。BメロからサビにかけてはD ionian、つまりDメジャースケールが使用されています。
トニックが変わらないこのようなモードチェンジを転調とみなさないのであれば、転調せずに複数の旋法を使用している楽曲の例といえます。トニックをDで一貫させることで、それぞれの旋法の色がわかりやすく楽曲に表れています。
もちろん、各旋法への移行へは丁寧な処理がされていますので、それなりの工夫は必要です。mixolydianがaeolianからionianへの橋渡し的に機能していることもポイントかと思います。
また、あまりionian臭くならないようになのか、サビではAを基準にしたメロディ構築がなされていますね。(ですが、コードワークがDメジャーを意識されているので、やはりDメジャースケールと考えて差し支えないかと思います。)もちろん、一貫して使用することもあります。森のキノコにご用心(スーパーマリオRPG)では旋律にDb dorianが一貫して使われています
つまり、旋法というのは曲想に合わせて自由に切り替えたり切り替えなかったりしてよいものといえるでしょう。しかしその旋法を使用していることが分かるよう、それぞれの特性音を意識したメロディ作りやコードワークが重要になってくると思います。
〇それともコード上で適用されるものなのか
あるコードに対しスケールを適用する考え方は、即興演奏などでどの音を弾いてよいのか簡潔に伝えるため、あるいは理解するために使用される場合が多いという認識です。
①の例を取り上げますと、Cメジャーコード上でC mixoとC lydianを別プレイヤーが同時にひいてしまうと、FとBの音が衝突してしまいます。この時にどの音を鳴らしてよいのかを伝えるのに旋法を借りた表記は非常に便利です。また、コードのルート音をスケールのルートとすることで、それぞれの音の役割がわかりやすくなります。たとえば、Cメジャーコードに対しD mixoを鳴らすことを考えますと、どれがコードトーンでどれがノンコードトーンなのか一発で判断するのはなかなか難しいと思います。ですが、CメジャーコードでC lydianが鳴らせると考えると、コードトーンとテンションが一発でわかります。このような認識は即興演奏において非常に便利です。(私はプレイヤーではないので実際のところはわかりませんが、そういうものと認識しています)
また、ほかの回答者さんもおっしゃっているように、7thコードなどのドミナントに対しオルタードスケールを想定するなど、コードネームだけでは見えていない音をプレイヤーが自由に解釈できるツールとしても機能します。(この場合、ほかのプレイヤーとどのように意思疎通するのか、私も知りたいです)
つまり、コードに適用されるスケールはあるコードの上でどの音を弾いてよいのか、または弾こうとしているのかを解釈したり、表現したりするための方法の一つだといえると思います。
以上、このように考えてみました。
-
投稿者投稿
このトピックに返信するにはログインが必要です。