Ⅵm9/IV→Ⅱm9/♭Ⅶ→ ♯IVm9/Ⅱ→♭Ⅱm7/♯IVという進行
- このトピックには3件の返信、3人の参加者があり、最後に
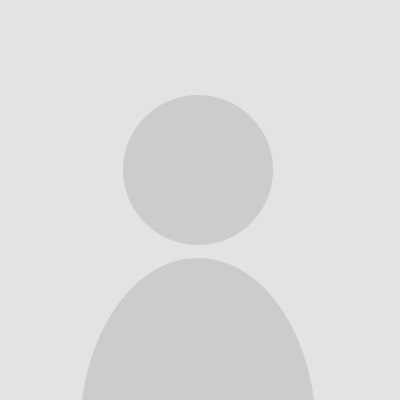 taro yamadaにより4ヶ月前に更新されました。
taro yamadaにより4ヶ月前に更新されました。
-
投稿者投稿
-
2025.6.15 21:07
自分の過去の曲で
Ⅵm9/IV→Ⅱm9/♭Ⅶ→
♯IVm9/Ⅱ→♭Ⅱm7/♯IV
と進行しているものを発見したのですが、正直何で成立しているのか分かりません。
メロディが後半の2つのコードから短三度下に転調しているので、実質IV→♭Ⅶ→(転調後の)IV→Ⅵmみたいな進行という事は分かるのですがそれ以上の部分が分からず過去の自分に困惑しています。
何故成立しているのでしょうか、、、
2025.6.21 20:41仮に、構成音に関する疑問だとするならば、前半部分の分数コード進行(Ⅵm9/IV→Ⅱm9/♭Ⅶ)を[IVM9(♯11)-
♭VIIM9 (11)]というルート音に対するテンションコードとして再解釈してあげれば解決できそう。つまり、このとき、一時的にkey=IV majorのモーダルインターチェンジが働いてて、そのおかげ(?)でIVの「♯11」がリディアンの構成音(あるいは、アヴォイドノートの回避音)として調和する。
そして、key=IVとみるならば、♭VIIへの移行は、「I-IV」の模範的な進行となり、M9(♯11)という構成音も、少し複雑な響きとなるけれど、一応は解釈できる。
あとは、ひゅーぶさんの解釈どおり、後半は実質IV-VImの響きになるのかな。て感じですb。まぁ、あくまでも機能和声論に従えばって感じですが※追記
失敬、前半部分の2つめの和音は、正しくは♭VIIM9(♯11)ですね。僕自身は、この和声を♭VII Lydian Clusterって呼んでます。♭VIIリディアンスケール上を適当に鳴らしてますので……
2025.6.22 04:18ご回答ありがとうございます!
最初に書いたコード表記が本当に分かりにくくて申し訳ありません。
(制作当時のメモ書きに例の表記で残されていたので、なにか糸口になるかとそのまま書いてしまいました、、)
(最初から貼れよという感じですが)当該箇所のリンクを貼ります。
https://youtu.be/9_pWwfK1KZg?si=zPGS-gKEOqJ4GhFi&t=113
どうやらサビのⅣ→Ⅴ→Ⅵm→♯IVdimという骨格を元に変形しているようで、
Ⅴを♭ⅦM7にリハモ→
Ⅵmを同主長調のⅥmである♯IVmに変更→
それに伴い♯Ⅳdimを♯IVmに変更→
ベースに動きをつけたくなり1つ目の♯IVmをⅡM7に変更
と言うようなプロセスを経て最終的な形に落ち着いた、と言うような考察をしています(自分の曲なのに何で分からないんだ、、、)
分かりにくかったら申し訳ありません🙇♀️
自分も釈然としない点が多々あるので気になる点あればご意見くださるとありがたいです。
2025.10.3 02:42順に考えてみます。元の進行はこのようになっています。
元進行:VIm9 / IV -> IIm9 / bVII -> ♯IVm9 / II -> bIIm7 / #IV
VIm9 / IV, IIm9 / bVII, ♯IVm9 / IIはそれぞれベースに対して長三度上のマイナー9thコードが乗っているので同じクオリティのコードとなっています。
ルートからの度数を確認すると[M3, P5, M7, M9, #11]となっています。これはM9(#11)コード、つまりリディアン系の響きをもつコードと考えることができるでしょう。
このような三度系のスラッシュコードはまず特別な理由などなければ分割せずに表記し、(今回の場合)M9(#11)として書くほうが自然だと思います。それを踏まえコード表記を書き直すとこうなります。
degree:IVM7(#11) -> bVIIM7(#11) -> IIM7(#11) -> bIIm7 / #IV
原曲を聞かせていただきましたが、ぱっと聞いた感じKey = Db(Bbm)っぽかったのでin Dbでコードネーム表記するとこうなります。
in Db:GbM9(#11) -> BM9(#11) -> EbM9(#11) -> Dm7 / G
次にbIIm7 / #IVを考えてみます。ルートからの度数を確認すると[P5, m7, M9, P11]なので7sus4系のコードといえそうです。
かりに7sus4としてみてみると進行が整理されて見えてくるかと思います。もう一度表記しなおします。
degree(in Db):IVM7(#11) -> bVIIM7(#11) -> IIM7(#11) -> #IV7sus4
コードネーム:F#M9(#11) -> BM9(#11) -> D#M9(#11) -> G9sus4次に転調先が短三度下(パラレルメジャー)ということでKey = Bbでの表記も考えてみます
degree(in Bb):bVIM7(#11) -> bIIM7(#11) -> IVM7(#11) -> VI7sus4
次に、そもそもの問いである「なぜ成立するか」について自分なりに考えてみます。
何をもって成立とするかは難しいところではありますが、ここでは自然に聞こえること = 接続が自然、転調感が少ないとして考えてみます。これにはいくつもの要因があると思います。
〇事前にパラレルメジャーへの転調の伏線がある
今回の分析対象のコード以前に(in Db)IV -> V -> VIm -> #IVmが鳴っているというのが一つポイントだと思います。(#IVdimとおっしゃっていましたがメロでDがなっているっぽいので#IVmと聞くのが自然かと思います)#IVmはパラレルメジャーの借用と考えることができますので、前提としてパラレルメジャーのほうへ調性が傾いており、転調が自然に受け入れやすい地盤ができているように聞こえました。〇転調先が自然である
転調の中でも特にトニックを共有するパラレルマイナーやパラレルメジャーは転調感が出にくいと感じます。分析ではkey = Dbとしてますが今回の楽曲はBbmよりの作曲となっているためよりパラレルメジャーへの転調が自然なものとなっています。〇F#M9(#11) -> BM9(#11) -> D#M9(#11)が平行移動の関係である
M7(#11)というのは安定した和音であり、安定した和音の平行移動は比較的自然に聞こえます。
特に今回の進行のようにお互いに共通音を持つ進行ではより自然な進行に聞こえます。〇和声機能としてあいまいである
BM9(#11)の登場で調性があいまいになったまま、特に解決せずにKey = Bbのコード進行へ移行しているように見えます。
このため和声機能があいまいになり機能を持っていないように聞こえますが、前述の和音の安定性のために自然に聞こえます。
特にBM9(#11) -> D#M9(#11) -> G9sus4のところでは明確な機能感は感じられずサブドミナントが継続して鳴っているような響きに聞こえます。G9sus4もルート音だけ見るとトニックに見えますが、7sus4系であるためサブドミナント的に聞こえます。また、後半のIVM7(#11) -> VI7sus4(in Bb)はBbメジャースケールの構成音にすべて含まれるので転調後のコードとして自然に聞こえます。(もともとの作曲意図としてKey = Bbを転調のターゲットとしているのであれば、これはごく自然なことと思います)
ほかにも編曲的な観点からいくつか考えてみます。
〇メロディがリードしている
メロディラインが和声進行や転調を補助しているため自然に聞こえます〇編曲やMIXの影響
コードの音がアルペジオ的に散らされているので、はっきりM9(#11)が平行移動している風には聞こえず、スケール的な響きとして和声感が感じられるにとどまっています。そのため、ルート音が強調されてD#M9(#11)がII(in Db) / IV(in Bb)とピボット的に聞こえる…かもしれませんまとめますと、
・前提としてパラレルメジャーへの下地がある((in Db)#IVm )
・(in Db)bVIIM7(#11)が転調の前準備として調性を揺るがすように機能している
・理論的に明確に指摘できるような転調のシーンはないが、機能論的な役割より和音そのものが持つ響きを優先したコード選択により、あいまいに転調している
・共有音を持つことで進行を自然にしている
・ほかにも編曲的な要因で自然な進行を実現している弱進行を利用したあいまいな転調といった感じでしょうか。こういった実践的な「聞いて成立する進行」は面白いですよね。弱進行やサブドミナント的な響きは奥が深いです。
-
投稿者投稿
このトピックに返信するにはログインが必要です。