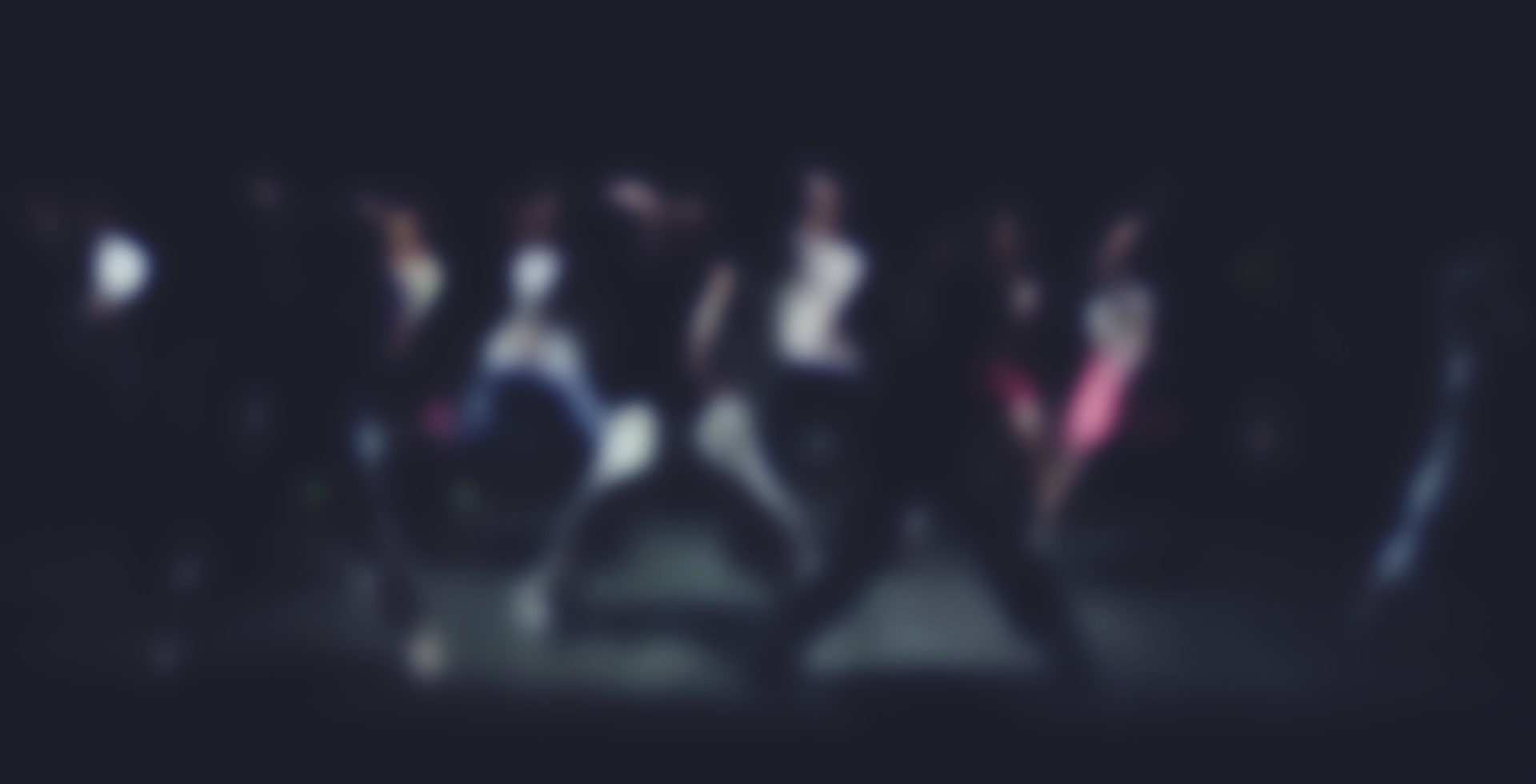目次
4. ハーモニーの選択
先ほど見たとおり、フリジアン中心の楽曲においては、iii音の長短スイッチングは頻繁に行われます。加えてそれ以外の音度でルートに対し3rdを乗せる場合も、メジャーなのかマイナーなのかの選択にフレキシビリティがあります。実際にいくつかのパターンを見てみましょう。
メジャーの平行移動
新しい学校のリーダーズの『Tokyo Calling』は、典型的なフリジアンのベースラインから始まります。サビになるとそのラインに対しハモリが乗るのですが、そこでは常にメジャーコードが形成されます。
結果、ベースラインだけを見れば常にフリジアンですが、全体で見るとii音とiii音の長短がその都度コロコロ切り替わるようになっています。
主和音がメジャー化するというのは、同じ♭2nd系の音楽でいうとフラメンコにあるスタイルで、スパニッシュ・エイトはまさにその象徴ですが…
ただ『Tokyo Calling』ではフリジアンにとっての特性音である♭2nd自体も状況により解除してしまうということで、その毛色は大きく異なります。これはどちらかというと、テクノやハウスでのシンセの無機質な平行移動を思わせます。
フリジアンにおけるハモリ構築をどうする?という課題への解答のひとつとして、インスト音楽の手法を歌に転用するというアイデアがあるわけですね。
パワーコード
一方で、ロックと同様に3rdの長短自体を余計なものとして避け、パワーコードを構築する曲もありました。
cosmosyの『zigy=zigy』は従来的なコード進行に基づくAメロ・Bメロからフリジアンのサビに入るという、いわばHow You Like That型の構成をとる一曲。そのではサビにおいて3rdがなく、メインメロディに対しハモリが5thとオクターブ上のRtをとるという構図になっています。
4度・5度のハモリはオリエンタルな空気を醸しますし、また音階のiii音が提示されないのもまた、『君が代』のように日本を含めた非西洋音楽の音階で見られる特徴なので、ここは意図的に日本的なテイストを演出するための3rd抜きというチョイスなのではないかと思います。
ハイブリッドコードの平行移動
面白かったのがLE SSERAFIMの『CRAZY』で、この曲ではナインスコードを3rd抜きで平行移動させています。
主和音の時にはたまにマイナーの3rdが鳴っているようですが、他は基本的に3rd抜き。スラッシュコードで表した方が分かりやすい、いわゆるハイブリッドコードの状態になっています。
主和音がナインスコードとなると、これはご覧のとおりフリジアンを否定するM2ndが構成音に含まれることとなります。そうでありながらもベースラインはフリジアンで進んでいく。こういうマイナー系列の平行移動もやはりテクノの方面でよく使われる技法ですね。
『CRAZY』はMVや振り付けを通じて全体的に“ヘンテコ”な世界観を提示していますが、音楽においても従来的な調性感の希薄な3rd無しの平行移動は無機質でどこか不気味な空気を湛えていて、今やありふれたものとなったノーマルなフリジアン音楽からは一線を画す演出に成功していると思います。
長短同時鳴らし
aespaの『Supernova』は、最初のサビは主和音だけがメジャーになる“フラメンコ方式”で進みます。しかし1:15からシンセのアルペジオが入ると状況が変わり、1小節のうち前半がメジャー、後半がマイナーという目まぐるしい変化をつけるようになります。そして2番サビはギターのフレーズがマイナーの3rdをしっかりと提示して、マイナー方面に落ち着いたかと思われたのですが…後半(1:37)からは1番と同じくメジャーコードのパッドが加わり、メジャーとマイナーがいっぺんに混在する状態になるのです!
キーの3度の長短が混ざるというのは、音響的には例えばブルースと似たところがあります。ただ文脈的な解釈としては、フリジアンとフリジアン・メジャーが混在する環境がK-Popにとって当たり前になっていった結果の産物と見るべきでしょう。
小まとめ
というわけで、コードの選択に関してはほとんど限りない自由があります。同じフリジアンのベースラインに対して異なるハーモナイズをする可能性も十分あるわけで、1番と2番でハーモニーを変えるという手法も考えられますね。またその際にiii音の長短スイッチングを簡単にするために、メロではiii音を避けて動くといった戦略もありえます。
5. 多旋法のバリエーション
もうひとつ、現行のK-Popの大きな特徴になっているのが、パートによって音階が分離する現象です。先ほどのHow You Like Thatでも、基本がフリジアンでボーカル群だけがエオリアンというような混在状況がありました。
これは、楽曲が複数の旋法を同時に使用している状態、すなわち多旋法Polymodal/ポリモーダルの技法を用いた楽曲であると捉えるのがよいでしょう。そこでここからは、何の音階と何の音階が組み合わさっているかに関するパターンを見ていきます。
フリジアン×エオリアン(マイルド)
最も典型的な多旋法の形態は、歌メロがエオリアン、ベースラインがフリジアンというスタイルです。Adoの『踊』のような日本の大ヒット曲でも既に導入されている手法であり、正直言ってこれはもはや遭遇しても驚かないくらいあちこちで見かけます。ただ競合するフラットとナチュラルのii音にどう折り合いをつけるかには差があって、まずはマイルドなケースから紹介します。
LE SSERAFIMの『ANTIFRAGILE』はフリジアンからスタートし、Aメロ後半(0:36-)でメロディがエオリアンとなり、フリジアンを保つベースラインとの多旋関係が発生します。しかしフレーズを分析すると、競合するii音を同時に鳴らすことはせず、タイミングをずらすことで直接的な濁りを生じさせないようにしています。
Fフリジアンの特性音であるg♭と通常のFマイナーキーのg♮がぶつからないように、8分音符ぶんずらしてギリギリで回避していることが分かりますね。こうなると一応理論上は「すごいスピードでエオリアンとフリジアンを切り替えているだけ。多旋法ではない」という言い訳が立つくらいのラインに収まっていて、聴き映えをポップに留める折衷案として秀逸です。
フリジアン×エオリアン(ハード)
とはいえ多旋法の魅力が本領を発揮するのはやっぱり音のぶつかりが発生したときでしょう。なのでここでは、フリジアン×エオリアンの中でも最もハードな噛み合わせ方をしていた例を紹介しようと思います。
イントロはB♭フリジアンで、How You Like Thatと同様、主和音とその上を行ったり来たりすることでフリジアンを提示します。しかしメロディはナチュラルのii音をゴリゴリに連打するメロディとなっていて、ベースやプラックが奏でるフラットのii音とバチバチに衝突しています。
シ♭とシですから、これは増8度(増1度)のぶつかりです。非常に過激なサウンドですけども、しかし「ガール・ギャング」というタイトルや「タフじゃなきゃウチらの仲間にはなれない」「ウチらはいつも一歩先にいる」といった歌詞を聴くと、「増8度くれぇで日和ってるやついねえよなぁ!!?」と言われている気分になってきます((・-・´)))
従来の和声感に耳を順応させてきた人には、この同度の激突は気持ち悪く感じるかもしれません。しかしこうした音使いにリスナーの耳が曝され続ければ、やがてそれが当たり前になり、なんの変哲もないものとして受容されていく未来はそう遠くないと思います。
フリジアン×ドリアン
BABYMONSTERの『DRIP』は、まずヴァース3周目の歌メロ(0:24-)で、ii音での♮/♭の直撃衝突が見られます。ここまでは先ほどのエオリアンのケースと同じですが、しかしここでさらにハモリに注目してください。すると2回目の”I’ll be there mangseol-iji ma”の箇所で、3度上のハモリがファではなくファ♯をとっていることが分かります。音階のvi音が長6度ということは、これはドリアンモードの域に入っています。
エオリアンを標準とすると、ベースはそれよりも沈むフリジアン、歌はそれよりも浮き上がるドリアンということで、互いに逆方向へ離脱しているのが面白いところですね。
フリジアン・メジャー×アイオニアン
フリジアン×エオリアンのメジャー版に相当するような例も存在します。
BLACKPINKの『Pink Venom』は、フリジアン・メジャー1で始まります。しかしブリッジ(0:34-)からのメロディはナチュラルのii音をとり、メジャースケール(アイオニアン)のポップなフレーズがコテコテの中東風フレーズにかぶさる構図になっているのです。
なおこの曲では2:26-の箇所でもフリジアン×エオリアンの激烈な衝突があって、かなりスリリングなサウンドを放っています。
ロクリアン×フリジアン・メジャー
逆に、フリジアンよりもさらに暗い音階との混合も見られました。
0:22からのブラススタブは主音とフラットのii音をを往復する典型的なフリジアンですが、トラップビートが始まる0:32-に注目してください。
ベースはまずトニックのC音から始まり、♭3rdを示すE♭へ。またCへ戻った後、次はG♭へ飛びます。いきなりの減5度が禍々しさを放っていて、これは一応ロクリアンのエリアに突入したとみなせます2。
一方でリードのフレーズはiii音がメジャー、v音も完全5度で、これはフリジアン・メジャーです。しかもちょうどボーカルのシャウトがナチュラルv音をとった瞬間にベースはロクリアンの減5度をぶつけているという挑戦的な構成になっています。
その後ヴァースの間を通してこの二層関係は続きます。伴奏がメジャーの3rdで歌メロが♭3rdならこれはブルースのスタイルですが、これはその逆の関係です。ブルースが歌うメジャーキーでの♭3rdに「明るく見える社会の中に潜む悲哀」のようなものを見出すとすれば、アイドルが歌うマイナーキーでのメジャーの3rdは「暗い社会の中の希望」の表現として捉えても面白いかもしれませんね。
ナポリタンマイナー×琉球音階
こちら『RASEN in OKINAWA』はJ-Popというより完全にヒップホップなので今回の趣旨からは外れているのですが、非常に興味深いケースだったので紹介させてください。
まずトラックのベースラインがc♯とdを繰り返しており、三味線が下方の導音b♯、「エーイ」というボーカルチョップがeとf♯を提示しています。v~vi音が不在ですが、まあおおむねC♯ナポリタンマイナーと見ていい状況です。
そこへ中盤に登場するOZworldの歌(2:32-)は、c♯-e♯-f♯-g♯-b♯の5音からなるC♯琉球音階で歌われます。m3rdの「エーイ」は相変わらず鳴っているので、この時点で長短3度が混在する状態になっています。
ただ面白いのは、琉球音階が第ii音を持たないがゆえ、ナポリタンマイナーの中の♭iiとは衝突せずに共存している点です。ですからもし「エーイ」以外の要素、つまりベース、三味線、歌の構成音を合算すると、(vi度不在ながらも)ダブルハーモニックスケールが出来上がります。
しかし実際には、このようにパート間の構成音を合体させてひとつのスケールとみなすような楽曲分析は、今回の曲においては間違いなく不適切です。なぜならこの当該箇所の旋律はii・vi音不在の琉球音階であるという点に重大な意味があるのであって、他のパートと合体させてしまったらこの“沖縄”という最も重要な文脈が滑り落ちていってしまうからです。
縦の重なりが大前提の和声分析においては、パート間の構成音を合算することは当然の行為です。
一方で多旋法の音楽においては、ある音度が不在であることも旋法の重大な特徴である可能性がある。したがって、むやみにパート間の構成音を合算することができない。これも昨今の旋法音楽を分析するにあたってひとつ注意したいところですね。
フリジアン×マイナーペンタ
「合算しないことで見えるもの」という点からもうひとつ。MEOVVの『MEOW』は、ベースがgとa♭を繰り返す典型的なフリジアン調のイントロから始まります。一方で0:21-0:38のヴァースパートの歌メロをみると、ラドレミソ(g–b♭-c–d–f)の5音しか登場しないマイナーペンタトニックのフレージングとなっています。
先ほどの例と同じく、これはパートを合算すれば単純なフリジアンの楽曲と説明することができるでしょう。しかし実践論の観点からすると、特性音をベースだけに担当させ歌メロはペンタでキャッチーに仕上げるというメソッドはフリジアンをポップスに持ち込むひとつの解答として注目すべきところですよね。
ペンタのフレーズはJ-Popでもおなじみなので、LDH系アーティストのフリジアン楽曲でもこの取り合わせは何度か見られました3。中にはファは使うけどシは抜くというパターンも。それから、Bメロ(ビルド)で通常マイナーキーのコード進行を用いたパートに入っている間もメロはシを歌わないというケースも散見されました。そこには、一時的にナチュラルマイナーになっているにせよフリジアンの世界観を真っ向から否定するシ♮の音を出すのはちょっと躊躇われるというようなバランス感覚が垣間見えます。
このようにフリジアン楽曲の分析においては、単に全体を足し合わせた総体で見るのではなく、具体的にどのパートがどの音度を出し、どの音度は避けているのかというところまで着目すると、グッと見えてくるものが豊かになります。
小まとめ
ご覧のとおり、現行のK-Popで多旋法はもう当たり前の技法となっており、特にフリジアンのベース×エオリアンの歌というコンビネーションは局所的なものを含めると本当にあちこちで見受けられました。そして、旋法どうしが衝突する際の“ぶつかり方”の激しさの度合いはさまざまです。簡単にレベル分けをしてみると、次のような感じになるでしょうか。
| 衝突レベル | ぶつかり方 | 楽曲例 |
|---|---|---|
| 0 | 全員で同じ旋法を使う | CL – Hello Bitches |
| 1 | タイミングをずらして直撃を回避 | LE SSERAFIM – ANTIFRAGILE(ヴァース) |
| 2 | 直撃するが、ハモリなど目立たない音 | MONSTA X – GAMBLER(ドロップ) |
| 3 | 主メロと低音域のベースが直撃 | Ado – 踊(Aメロ) |
| 4 | 主メロとリード楽器が直撃 | BLACKPINK – Crazy Over You(ヴァース) |
| 5 | 主メロとコード楽器が直撃 | XG – GRL GVNG(ヴァース) |
同じ衝突でも、ベースのように目立ちにくい低音域がコッソリやるのと、近い音域でクラッシュさせるのとでは強烈さが違いますよね。ことK-Popのガールズグループ楽曲にとっては、この文字どおり“クラッシュ”の強度がガール・クラッシュの濃度に直結するというふうに考えても面白そうです。