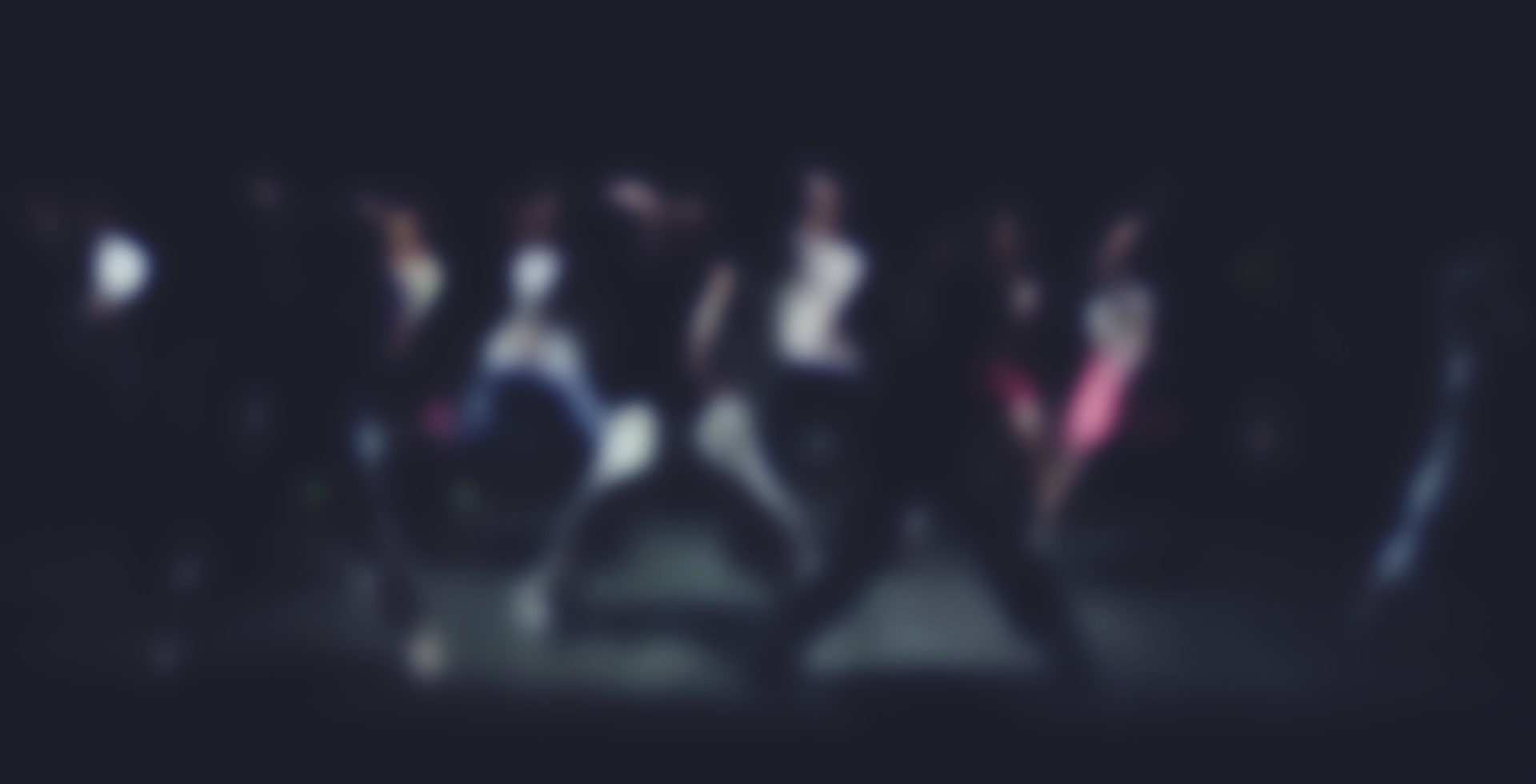目次
3. How You Like Thatから学ぶ
まずフリジアン式K-Popの様子を確認するために、代表的な一曲をとりあげて分析します。ターゲットとなるのは、2020年にリリースされたBLACKPINKの『How You Like That』です。
ぜひ改めて一度、どこでどの音階が使われているかなんてことに注目しながら聴き通して、それから先を読み進めてください。
イントロ: D♯フリジアン
まずブラスアンサンブルによるイントロは、主和音であるD♯mと半音上のEを繰り返しており、丁寧にフリジアンの提示をしています。この後いったん通常のマイナーキーに切り替わるわけなのですが、ここで一旦フリジアンのチョイ見せをしておくことが、いわばサビに対する伏線、布石のような機能を担っているのでしょう。
ヴァース: D♯マイナー
一方その後の歌メロではすぐにナチュラルのシの音が入って、従来どおりのマイナーキー音楽へと戻っていきます。4コードのループですがしっかりとしたコード進行が鳴っていて、ラップもなく、ここはかなり保守的な作りです。ここには2020年時点ではまだフリジアンがそこまで堂々とは居座れていないような、過渡期の残り香をちょっと感じます。あるいは、サビのフリジアンを引き立たせるための“あえて”の戦略かもしれませんが。
ドロップ: D♯フリジアン×エオリアン
ドロップ(サビ)に入るとベースやブラスがフリジアンのフレーズを奏で始めるのですが、注目すべきは歌メロの音取りで、”You gon’ like that that that”の部分はナチュラルのシを用いた旋律、つまりはエオリアンになっています。しかもその直後にはすぐにフリジアンへと路線変更するのです。
ここに「フリジアンでのメロディ作りどうする?」に対する“解答”のひとつがあって、すなわち「ベースやリードがフリジアンでやっていても、合間にサッとエオリアンを挟んじゃえばいい」という手法です。こんなふうに一瞬だけ都合よく音階を切り替えるのは暴挙に思えるかもしれませんが、よく考えたらナチュラルマイナー/ハーモニックマイナーで我々は長年カジュアルに、相当フレキシブルにソ/ソ♯を切り替えてきました。シ/シ♭をスイッチする行為はそれと全く同類の行為なのだから、何もおかしくないことに気がつきます。フリジアン/エオリアンの関係性をハーモニックマイナー/ナチュラルマイナーに似たものだと捉えると、少し実践の手助けになるのではと思います。
そのようにしてみると、フレーズの前半がエオリアンで最後の締めがフリジアンという流れも、フレーズの終わりにかけて中心音への引力を高める所作と見れるので、非常に合理的かつ効果的な動きに思えてきます。
それからもうひとつ見逃せないのが、偶数周回にてベースがi–iv–v–iという伝統的なT–S–D–Tのモーションを形成していることです。
フリジアンの属和音といえば、ディミニッシュになってしまうがゆえケーデンスをビシッと決めにくいという印象があるかと思います。確かに三和音や四和音による和声連結の世界ではそうかもしれませんが、しかしベースとリード(歌)の二声のみで、縦よりも横の繋がりが強い条件下では、このようなモーションも容易に可能であるようです。
- 二声のフリジアンT–S–D–T トラップビートを添えて
こちらのサンプルではあえて3rdを全く鳴らしていないのですが、パワーコードよろしくこうやって和声感を希薄にすると、フリジアンのケーデンスも何ら不自然なものには聴こえません。もちろんミ-シ♭の関係は不安定ですが、D–Tは緊張-弛緩のモーションなのだから、不安定であることはメリットともとれます。
アレッ……? ていうか我々、トライトーンの推進力が欲しくてわざわざVをV7にするわけですよね。でもフリジアンだったらそんなことしなくても最初から属和音にトライトーンが含まれてて、それって最強なのでは・・・・・??
……まあそれはそれとして、こうしてお望みならばベースを進行させて従来どおりの機能的な進行感をもたらすことができるというテクニックは、押さえておきたい大事なポイントですね😇
2番ヴァース: D♯フリジアン・メジャー
さて話を戻しまして、2番はラップが始まりますが、同時に音階面でもひとつ展開が作られていて、リード楽器の方でiii音がメジャー化して、フリジアン・メジャーの演奏に切り替わっているのです!
面白いのは、コード楽器が全く鳴っていないため、この差異が発現するのはリードのフレーズがiii音を通る瞬間のみであるという点です。そうであるがゆえ、旋法の長短転換という大イベントが起きているわりには、雰囲気の印象差はそこまで大きくありません。結局コード楽器が鳴っていない以上「主和音がメジャーになった」というのはほとんど理論上の話でしかなく、音響上はむしろ「フレーズに増2度のステップが生まれた」という方が楽曲に影響をもたらしています。この辺りは本当に、和声が大前提の音楽理論脳から少し切り離して考えなければいけないところだなという感じがします。
最終パート
以降は同じパートの繰り返しなので目立つところはありませんが、終盤一箇所だけポイントがあります。2:29の”Yeah yeah yeah yeah”のところは2声の3度ハモリになっていますが、ここはエオリアンでハモっていますね。周囲の楽器たちは完全にフリジアンであるにもかかわらずです。
こういったパート間の音階の分離は近年のK-Popに本当によく見られます。この曲では音階どうしの食い違う構成音が直撃することは避けられているので比較的マイルドな部類の分離になりますが、中には同時に音が衝突するパターンもあって、それはこの後紹介していくことになります。
金字塔としての存在
ひととおり分析をしてみると、How You Like Thatがこの一曲で既にかなりの“解答”を提示していることが分かるかと思います。しかも音楽に加えて映像との対応で見ても、このMVはフリジアン周辺のモードがどんな表現に適しているかを示す教科書となっています。
フリジアンのイントロではかがり火と紫色の翼のオブジェが荘厳な雰囲気を演出し、それが一転してエオリアンのヴァースに入ると水色の背景と光の表現で落ち着いた水面を思わせます。さらにドレスや花といったフェミニンな要素がひととおり続いたあと、いきなり目出し帽というゴリマフィアアイテムが出てくるやいなやフリジアンのドロップに入ります。

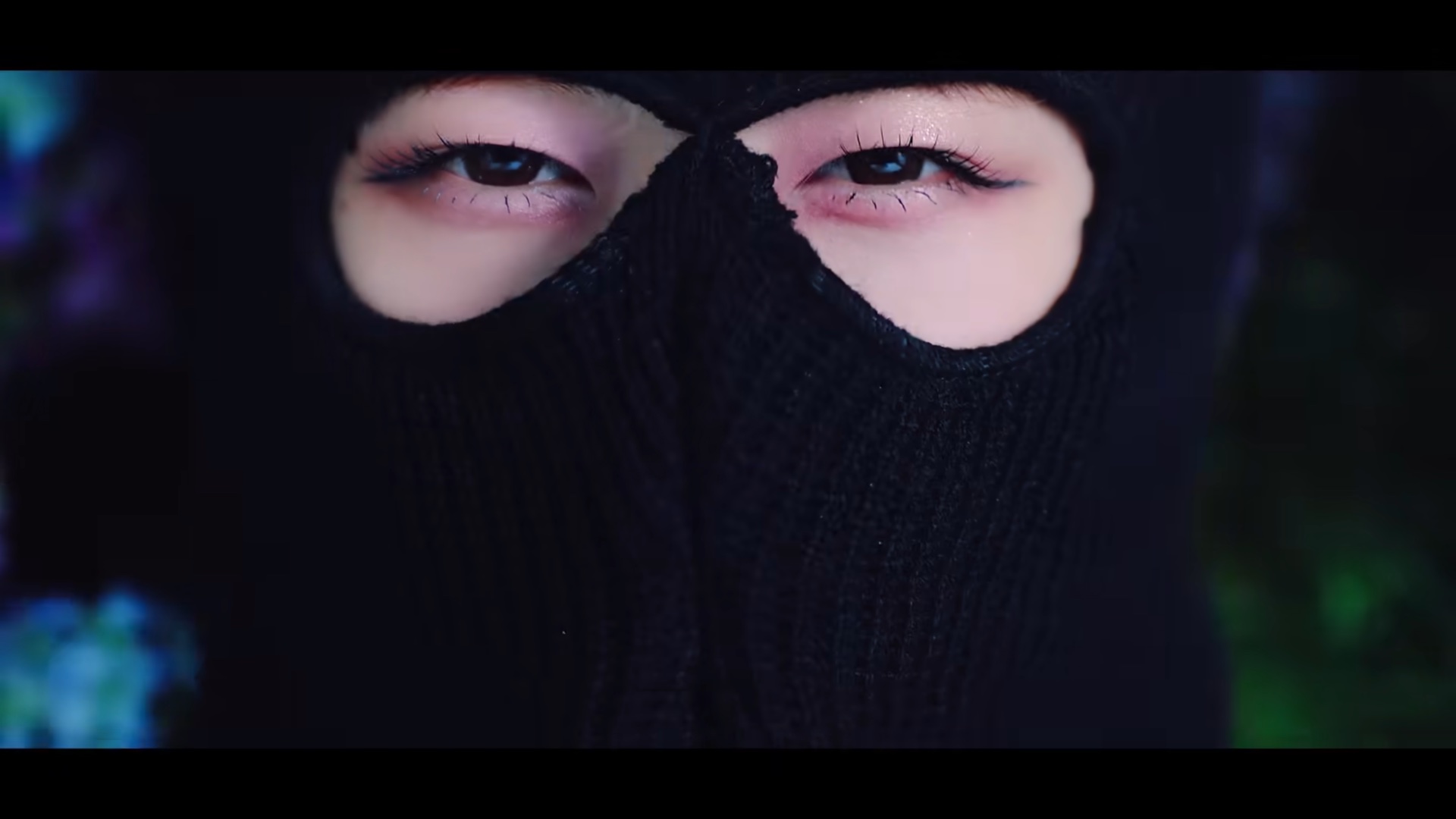
BLACKPINK – ‘How You Like That’ M/V (https://www.youtube.com/watch?v=ioNng23DkIM)
転換した場面は原始を思わせるド緑のジャングル風植物たちと茶色のじゅうたん。服装もファーコートにデニムにビカビカの金アクセと、ヒップホップ的なセルフボーストの感が全面に現れます。そして極めつけが、フリジアン・メジャーと同時に登場するロバ(?)と中東の街並みです。


(同上より)
これを見れば誰にでも分かります。フリジアンにはヒップホップ的な文脈が織り込まれていて、それを纏わせることで非常に分かりやすくガール・クラッシュを打ち出せること。iii音をメジャー化させると中東みが立ち現れるので、アジア人の我々がこれを活用することでアジアの民族性を自然に盛り込めること。そしてエオリアンを従来的なポップス手法としてガール・クラッシュを際立たせるためのフリに使えること。
How You Like Thatはダンスパフォーマンス動画の方と合わせると再生回数は30億回、Spotifyでも11億回と、文字どおり“桁違い”のヒット曲となっているわけですが、この“教科書”が世界に配られたことは、その後のフリジアンの隆盛を決定づける基盤のひとつになったのではないかと思います。
この曲より以前でも似た内容の曲はあります。でもある音楽の型が一時代を築くには、ダイレクトなフォロワー楽曲が続々現れるような爆発的なヒット曲が必要です。K-Pop界に金字塔のようにそびえ立つHow You Like Thatの存在は、それ以降のソングライターたちにとっての明確な参照点になっているはずです。
実際に昨年BABYMONSTERが『SHEESH』をリリースした際には、How You Like Thatのコピーであると批判が起きたそうで、そんなエピソードからもこの曲の存在感のデカさが伺えます。そして、ただトラップビートにフリジアンを乗せるだけでは「How You Like Thatの模造品」になってしまうというその環境こそが、なおのことフリジアン・ポップスを多様化へと駆り立てているのかもしれません。
ではここからは、色々な曲の特徴的な部分をピンポイントで切り取って細かな技法を見つけていきます。